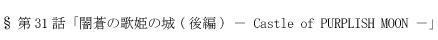
『正門が開きました!!』
ひびきたち3人は、カレンの言葉に耳を疑った。エーアスト隊は、いまだ奇声蟲の群れに阻まれていたからだ。
『響様の隊が、北側の城壁の亀裂から城内へ入られたそうです。
結界のためか、門が開くまでラナラナ様でも状況がよく伝わってこなかったらしいです。
内側から開門した途端に、貴族種が率いる群れが城外外から入り込んだそうです。その直前には、緋色の奏甲がいたとか、それと戦ったとか・・・。』
「なによそれ、わからないことばっかりじゃない。」
ひびきは要領を得ないカレンに、言葉で噛みついた。
『いこう!ひびき。ここからなら、援護があればすぐつくわ。』
「ちょっと待ってディーリ。カレン、響たちは!?」
『えぇっと。』
不機嫌なひびきに、どう言おうか迷ったカレンの代わりに、ソルジェリッタが冷静に答えた。
『響様と和司様は無事です。』
ソルジェリッタは、知っていたにもかかわらず、ナルドが戦死したことを言わなかった。
『とはいえノイズがひどく、ティリスの結界の影響もあり、無事であること、奏甲も深刻な損傷はないということくらいしか、ラナラナにも判らないようです。』
「響は無事なのね。」
『ええ。ですが貴族種率いる一群が正門から侵入したという状況は事実のようです。お2人の危機が去ったとは言えません。』
ソルジェリッタは言った。ひびきは一瞬、息を詰まらせる。そこへリフィエの言葉が割り込んだ。
『カノーネ司令の号令がかかっています。先鋒の5小隊は周囲の奇声蟲にかまわず、正門を目指し、城内へ突入せよとのことです。それ以外の隊は、突入部隊を全力で援護せよと。』
「行くわ、ディーリ、玲奈。ソルジェリッタ、よろしくね。」
『もちろんです。ひびき。』
ひびきは、結界とノイズによる調律の不確実を不安に思った。ただでさえ彼女の歌姫であるソルジェリッタは、はるか東の王都ルリルラからリンクしているのである。
だが、不安を表に出さないよう、凛々しい声でひびきは号令をかけた。
「エーアスト隊、続いて!」
エーアスト隊が進攻の矛先を変える。部隊の先頭は、立ちふさがる衛兵種だけを払いのけ、止まることなく前進する。衛兵種とはいえ組織的に襲いかかってくる敵は手ごわい。それを後ろに続く部隊がひきつけ、貴族種には矢や槍を放ち、突入部隊から気をそらそうと試みる。
エーアスト隊そのものが、一本の槍となって紫月城の正門へ突き進んだ。
「響!どこ!?」
正門へ近づくと、ひびきはブリッツ・ノイエを探した。貴族種の姿は見えないが、それでも衛兵種の動きは統制が取れ、手ごわい。後ろに続く奏甲の数も多くはなく、援護が減った分だけ相手をしなくてはならない周囲の奇声蟲の数は多くなっていた。
ソルジェリッタがミリアルデ・ブリッツを起点に周囲の奏甲を走査してから、言った。
『ひびき。正門に向かって右、城壁に沿って最初の塔の基部に、ブリッツ・ノイエがいます。響様です。塔を背中にして、防戦に努めていらっしゃいます。』
ソルジェリッタの言ったとおりの場所で、両手で剣を操って奮戦するブリッツが、ひびきにも見えた。
『それから城門の内側、中庭にリーゼ・ミルヒヴァイスとシャルラッハロート・ツバイが各坐しています。リーゼはもう動かないようです。奏座が酷くやられて・・・これでは機奏英雄は助からないでしょう。もう・・・奏甲も感じられなくなります。』
「それって・・・、『ナルド』だっけ、響の部隊でおっきい奏甲に乗っていたのって・・・。」
『そうです。』
「ブリッツは、向かって右ね。」
ひびきは、人の死の実感を抱くのを恐れるかのように、響の無事を確認する行動に逃げ込もうとした。
いままで、絶対奏甲の損傷や破壊は戦いの中で多発したが、死者は数えるほどだった。それは奇声蟲に対しての奏甲の有用性の実証でもある。だが戦死者の少なさゆえに、ひびきが個人として知っている戦死者は、ナルドが初めてであった。
「響、生きてる!?」
『ひびき。じゃ、ハルフェアはもう正門まで来たのか。』
「違う、あんたがヘマやったからエーアスト隊だけで突撃してんの!わかってんの、迷惑かけて!」
『赤いシャルラッハロートがいて、ナルドはそいつにやられたんだ。』
「なに言ってんのよ。敵は蟲でしょ!それに緋色の奏甲は、集会場で助けてくれたわ。」
『違う。ほんとなんだ。何か違うことが起きようとしてる。行かなくちゃ。』
正門前は乱戦となっていたが、エーアスト隊の活躍で確保はされつつあった。奇声蟲は城内へ逃げ込むように見える。
そのなか、ブリッツ・ノイエが塔から離れ、正門を入ろうと移動を始める。
「違うことって、なによ?響っ、ちょっと待ちなさいよ!」
『勇ましいこったねぇ。ハルフェアの隊長さんたちは。だがな、正面からの一番乗りは、このコーダ・ビャクライがいただくぜ。』
別の男の声が割り込んだ。若くはないが、老齢でもない張りのある成人男性の声。それとともに、戦場に見慣れぬ奏甲と部隊が展開した。そのほとんどが、黄金の工房から運ばれてきたプルプァ・ケーファや、シャルラッハロート・タイプであるのは、ひびきにも判る。
だが、彼らを率いる大型の奏甲は知らない奏甲だ。それは突起が多く、禍々しささえ感じさせる。闘牛のような角の間に、さらに前方へ伸びる三本目の角が備わる頭部。フェイスは他の奏甲に比べてはるかに人相が悪い。機体各所にはスパイクがいくつも備わっている。背中には2本の支持肢で支えられた、鋭角な突起がある半月状の板が左右一組あり、長い腕で武器を振るったり、急激な回避を行う際、翼のように稼動してバランスをとるのに役立っている。その姿から、ひびきは「悪魔」という言葉を連想した。
『てめぇら、ぐずぐずすんな!現世騎士団の力を示すんだ。正門を突破するぞ!』
その先頭の奏甲は、瞬く間に立ちふさがる奇声蟲を蹴散らして進んできた。だが異常なのは、率いている奏甲が脱落したり、奇声蟲に取り付かれ立ち往生するのを無視して、おいていってしまうことだ。ハルフェアの部隊のように、バックアップする部隊がいるわけでもない。まもなく、その奏甲が正門に入ることをひびきと響が見届けたとき、追随していた奏甲は、片手に足りるほどの数でしかなかった。
『あれが、現世騎士団か。』
「乱暴な連中ね。ディーリ、玲奈。きてる?」
『もちろんよ。』
『ごめんなさい。すぐ行きます。』
すぐ近くまで来ているのはディーリのシャル2だった。ひびきと響も正門に到達し、現世騎士団を追うように正門を入った。
門を入った中庭では、激戦が繰り広げられていた。中門寄りに貴族種が陣取り、その周囲を衛兵種が隊を組んで現世騎士団の奏甲を襲っている。だが、貴族種は片側の足を、失ったり傷を受けており、その場を動けなくなっているようだった。その赤い表皮には、剣の傷のほかに、焼けたような黒い部分も見えた。
『緋色の奏甲、あいつがやったのか・・・。剣以外は・・・魔法?歌術か?』
響のつぶやきが聞こえた。ひびきにはその貴族のほかに、各坐したリーゼとシャル2が見える。両機は中庭の端で放置されていた。稼動して戦うことができる現世騎士団の奏甲が、先に相手となっているためだ。
ひびきたちは、正門に入ってすぐのところで、衛兵種の一群の相手を余儀なくされ、玲奈が到着するまでその場で防戦する。
コーダと名乗った男の奏甲以外が、1機、また1機と倒れ、奇声蟲が群がっていく。引き倒された奏甲は、奇声蟲のあごによって装備や装甲を剥ぎ取られていく。その中で、とあるプルプァ・ケーファのコクピットが露出した。奇声蟲から伸びた触手が、コクピットに突きこまれ、ケーブルに断末魔の悲鳴がこだました。
その中でコーダの奏甲だけが、鬼神のごとく奇声蟲を殺していく。彼のキューレヘルトは盾は持たず、長さは異なるものの両手に剣をそれぞれ持ち、二刀流で隙なく切り払っていく。
『ああっもう、うぜぇ!このキューレヘルトの敵じゃねーんだからよっ!』
そう悪態をつき、そのままの勢いで動きが取れない貴族種へ肉薄していく。そのとき、玲奈のシャル2が正門へ取り付いた。
『ディーリさん、ひびきさん、ごめんなさい。』
「ううん。まだ戦える?」
『はい。大丈夫です。中庭に入ってしまいましょう。この子のハルバードは、狭いところでは使いづらいんです。』
「わかったわ。まずは、あの貴族を倒す必要があるみたい。いい?響、ディーリ。」
『いいよ、ひびき。』
『ああ、やっつけよう。それからだね。』
ディーリと響が答えた。
「玲奈は、私たち3人の背中を守って。長い武器なら、その方が戦いやすいでしょ。」
『わかりました。』
「じゃ、いくよ。それっ!」
4機の奏甲が、正門から中庭の中央を突破し、貴族種に迫った。
ミリアルデとブリッツという華燭奏甲が2機加わって、すでに自身の機動力を失っていた貴族種は瞬く間に退治され、残った衛兵種は正門から外へ逃走した。
無事だった奏甲は、ミリアルデ、ブリッツ、ディーリと玲奈のシャル2が2機、キューレヘルト、そして気を失っていて気付をされた和司のシャル2の6機のみ。
現世騎士団に生存者はいたものの、後続のハルフェア部隊が来るまで、動かない奏甲のコクピットで祈っているしかない。
そしてナルドのリーゼ・ミルヒヴァイスは、2度と動くことはなく、響は、奏甲の視界を介してとは言え、生まれて始めて、人同士の戦いで死んだ人の遺骸を見ることになった。
「響。あ、あのさ・・・。」
『黙ってて。いや、来ちゃダメだ。ひびきには見てほしくない。それに、これは奇声蟲と戦ってのことじゃないんだ。』
ひびきは、緋色の奏甲が助けてくれた時の様子から、いまだ響の言うことが信じられない。だが幼馴染が、怒りをこらえているのはよくわかった。いままで彼女の前で、響がこれほど昂ぶったことはない。ひびきは彼を疑うようなことを言い続けて、怒りを向けられるのはイヤだった。だから言われたとおり、黙っていた。