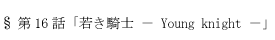
ハルフェアの統治者である女王ソルジェリッタは、はるか西のポザネオ島で戦う宿縁の機奏英雄、御空ひびきのため、王都ルリルラ宮のベランダで歌っていた。
その歌は単なる歌ではなく、戦場にあるひびきと、彼女が機乗する絶対奏甲ミリアルデ・ブリッツと調律し、その巨大ロボットが戦うことを可能とする、力のある歌なのである。これだけの遠距離で調律を有効とする歌姫の力は、幻糸の力満ちるアーカイア世界といえどもソルジェリッタくらいしか持ち合わせていない。それこそが、ハルフェア王家に身を連ね、「風の女王」の称号を身に受ける彼女の特異な能力でもある。
だが、その女王にして力のある歌姫の彼女が渋い表情をしていた。ひびきが彼女の歌を受け入れてくれないことと、現地でひびきの危機を救った緋色の奏甲について、思い当たる節があったからだ。
「緋色のシャルラッハロート・・・あれは姉姫さまの・・・」
<ケーブル>からの干渉を探り、思い浮かんだ人物が緋色の奏甲と英雄に調律している確信を得る。それは、ソルジェリッタにとっても能力的には見上げる存在である、さらに高位の歌姫の一人であった。
ソルジェリッタは、思わず閉じていた目を見開いた。身のまわりは、見慣れたルリルラ宮のベランダである。
『ハルフェアの派兵にわざわざ紛れ込んでくるなんて・・・。あの方は、いったい何をされようとしておられるの・・・。』
<ケーブル>に投げ込んでしまわないよう、その想いの声は小さい。
だが一番の心配は、パートナーのひびきである。調律がうまく行き、奏甲の中でも上級機である「華燭奏甲」であるミリアルデ本来の性能を引き出せれば、貴族種とさえ互角に戦えるとソルジェリッタは考えていた。その境地に達すれば、己の歌が届く限り奏甲に乗ったひびきの心配は不要になる。
「お加減はいかがですか、殿下?」
歌を途切れさせたソルジェリッタに、リトネが声をかけた。歌姫ではないものの、歌術についてはわきまえていて、歌術に関して時間を割く際、傍らに置くのはリトネか、もう一人とソルジェリッタは決めている。
「ええ、大丈夫よ。ひびきももうすこしで、わかってくださいますわ。」
皮肉がこもらないようにしてソルジェリッタは答えた。
再び目を閉じ、胸の前で手をあわせて集中する。ひびき、ミルアルデとの調律を維持する支援の歌を歌い続けなければ、貴族種を前にして戦闘起動していない奏甲など、ただの人形にも等しい。彼女は再び歌いだした。
ひびきは、ソルジェリッタの思わず漏れた言葉に気づかず、助けてくれた緋色のシャルラッハロートを見つめていた。
『ハルフェア自慢の華燭奏甲に乗っていながら、なんとも頼りない大将だな。コンダクターはどんなやつだ?』
<ケーブル>を経由して、ひびきのもとへ若い男の声が届く。その声には、ソルジェリッタともう一人、若い声の英雄のパートナーであろう歌姫の強い気配が感じられる。
「わ、わたし・・・」
『女の機奏英雄?いや、女の子か。ハルフェア女王の歌に、特別な剣と・・・調律のブースターアイテムを身に付けている。だから起動が障害状態なのに、ここまで動けるのか。それにハルフェアから、歌がここまで届くとはね。』
言葉で答えもしないのに、緋色の奏甲の英雄はひびきの状態を読み取っていた。ひびきの胸に、まるで裸を見られたような恥ずかしさが突き上げてくる。
「なによっ、勝手に人の状態を解説しないでくれるっ!」
『ごあいさつだな、助けたのに。まあ、成り行きだからいいか。
それより、歌姫の歌を音として聞こうとするな。<ケーブル>に耳を澄ますのはやめておけ。音に集中してしまうと「感じる」余地がなくなる。
奏甲の戦闘動作に集中すれば、自然に自分のパートナーの歌だけを感じ取れるようになる。それから敵を恐れないことだ。戦いはいつも、先に恐れ、戦う意思を失った者が負ける。』
「そんなこといったって・・・わかんないよっ。怖いものは怖いよっ。」
ひびきは視線の先に、緋色の奏甲の一撃から立ち直ろうとしている、貴族種奇声蟲を見ながら言った。
『自分が、怖いと思うことを認めるのはいい。だが恐れて腰が引ければ、奇声蟲じゃなくても敵はつけ込んでくるぞ。』
「なによ偉そうにっ。あなたは恐れることがなくって、あの貴族種もやっつけられるって言うのっ!?」
『貴族相手では、俺一人では難しいだろうな。
だけど俺の歌姫が、俺のために歌ってくれる限り、勝つまで戦うさ。』
 緋色の奏甲は、立ち直った貴族種に向かって剣を構え直す。
緋色の奏甲は、立ち直った貴族種に向かって剣を構え直す。一方のひびきは、決意を秘めた若い英雄の言葉に、声を出せないでいた。感動していたと言ってもいい。歌姫への絶対の信頼と、自分の努力をすべてを捧げるつもりで、それが必ず報われる、いや報われるまで戦うという決意を、<ケーブル>は伝えたのである。
この迫力で、あるいはこの瞬間に告白されていたら、ひびきはうなづくことしかできなかっただろう。アーカイアへ召喚されなかったら、そういう場面がありえたのは、彼女の預かり知らぬことである。だが、緋色の奏甲の英雄は、次に発した質問の答えから、奇しくもそれを知った。
『ハルフェアの大将っ、名前は?』
「えっ、ひびき。御空ひびき。」
『へえ、奇遇だな。知ってるよ。まさか音羽もいるんじゃないだろうな。』
緋色の奏甲、ひびきのミリアルデ、そしてディーリと玲奈のシャルラッハロート・ツバイの前方で、貴族種が無傷な側の目で緋色の奏甲を見つけ、姿勢を変えた。片目は閉じられていたが、もう一方の目に怒りが満ちていることが、ありありとわかる。
「私たちを知ってるの!?あなた、誰よっ?」
ひびきの問いに、答えを得る余裕は与えられなかった。数え切れない衛兵種を身にまとわり付かせ、手傷を負った貴族種が突っ込んできた。
『来るぞ!』
頭部の衝角を突き出し、進路上にいる衛兵種まで跳ね飛ばし、踏み潰し、あるいは衝角で砕きながら、手傷を負った貴族種は4機の奏甲めがけて突き進む。
ひびきはミルアルデに剣を構えさせていた。バカにされたという反発と、自分の質問をさえぎられたことへの腹立ちが彼女を支え、今度の切っ先は、震えることなく敵に真っ直ぐに向いていた。