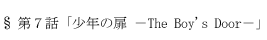
御空ひびきが風の女王のお茶会で翻弄されているころ、すこしはなれた原っぱで、一人の少年が大の字に寝っころがって、空を見上げていた。大量に湯気が上がる場所があるのか低い位置には"もや"がかかり、それらが、たまに吹く心地良い風に吹き散らされると、その向こうには吸い込まれそうな青空に、高い雲が屹立している。
それを目にしている少年は、だが空のことではなく、ここまでの自分の行動を思い出そうと頭を絞っていた。自分がこの草原に放り出されるまでに、こうなる原因があるのかと。彼は、昨日の夕方、好きな女の子に告白してしまったところから始めた。それだけが、彼の日常が、変わってしまった出発点に思えたからだ。
その時、イエスかノーかわからない言葉を残し、走って去った幼馴染みの女の子―御空ひびきを、彼は追いかけなかった。彼女の言ったことの意味が、良い返事なのか、悪い返事なのか、まったくわからなかったからだ。
そもそも告白したのは、三年生の先輩がひびきを狙っていると、友達に聞かされたためだ。幼いころからいつも一緒にいて、それが自然で、当たり前だった。聞かされた先輩が、学校の男子の間で名うての女たらしだと言われている人物でなかったら、気にも留めなかったかもしれない。
だが、友人の言い方が効果的だったか、高校二年生という時期がそうさせたのか、二週間ほど考えたあとで、音羽響16歳は、御空ひびきに告白することを決意したのだ。
ところが、その決意の報いは判断のつかない言葉だった。そのあとはもちろん一人で帰り、頭を悩ませた。自分ひとりの下校は、彼女が風邪をこじらせて寝込んだ時を除けば、覚えている限り初めてだった。
無情にも次の朝はやってきた。そして彼は初めて、寝坊で遅刻をしそうになった。毎朝、のんびり歩いて間に合う時間にひびきと一緒に登校していたのだが、この朝だけは朝食も食べないまま、自分だけで通学路を走った。
息をはずませて滑り込んだ教室に、もちろんひびきはいた。だが、ダッシュしてきた疲労と、遅刻せずに済んでホッとした気の緩みと、昨日の灰色の結末のために、彼女にどう話しかければ良いかわからない。
さらに悪いことに、話しかけることができない状態のまま、一日を過ごしてしまった。彼女の方も話しかけてくることはなかった。それだけではなく、授業も友達の話すことも、昼食のメニューも、まったく頭に残らなかった。
その日の授業が終るとすぐに、響は部活に顔も出さず学校を出た。繁華街へ足を向け、気晴らしをしようと考えたのだ。だが、集中力がない状態では、アーケード・ゲームで良いスコアが出るわけもなく、かえって気もそぞろな自分を自覚しただけだった。本屋でも立ち読みするコミックのストーリーどころか、セリフの関連さえ頭に入らない。アニメ雑誌も、いつもの情報収集するという意欲がわかず、手が出ない。
それでも劇薬的な気晴らしになるかと、普段は悪友に押し付けられる、親に見つかりたくない種類の雑誌を、学校の制服姿でも未成年であることをとがめそうにない、バイトと思われる店員のレジで購入した。買った雑誌をカバンに入れて、閉じた状態でバレないことを確認したうえで、うちに向かった。
夕暮れの気配もまだない時間の内につく。親に聞こえるよう、玄関から大きな声で帰ってきたことを告げ、二階の自分の部屋に上る。
着替えた後、買ってきた雑誌のページを繰っていたが、本当に紙をめくる反復運動でしかなかった。頭を占めていたのは、相変わらず幼馴染みの返事のことと、今日一日の自分のみっともなさだった。
晩御飯の支度ができたという母親の声が聞こえて、デスクの椅子から立ち上がりながら、手にしていた雑誌をベッドの上に投げ出した。18歳や20歳といった、響にとってはまだお姉さんというべき年齢の若々しい女性が、惜しげもなくその瑞々しい体を披露していたが、このときの響には効果を及ぼしていなかった。響は、ベッドの上で開いているページを無感動に見て、親に見つかるかどうか一瞬、考えた。食事の間に、わざわざ親が食卓を離れて部屋に来ることはない。自分が食事を終えて戻ってきてから隠せばいい、と結論し、そのままにしてドアへ向かう。
その雑誌が見つかるかどうかという心配をした自分までが、情けなくなってくる16歳の男子である。
「あー、どうしてよりによって『わからない』ことになるんだろ。まったく、授業の内容なんて、ぜ〜んぜん使えません〜っん。」
よく聞く曲のフレーズを口ずさみつつ、伸びをして立ち上がった。自らの親は言うまでもなく、ひびきは近所に住み、クラスも同じだ。気が進まないからといって、避けることもできない。それどころか、話をしないという避け方そのものが、相手に悪印象を与えたり、考えさせたりしてしまう。友達にも先生にも、それぞれに対して違うことを考えて、違うことを隠して、違う言葉を話さなくてはならないことが、猛烈に面倒臭く感じられた。
「『ここではないどこか、それは約束の場所。そして世界の果て。』ってなところが、あればなぁ。そんな世界でヒーローになるとかさ・・・アニメじゃない、ってか。」
ため息をつきながら、伸びをしたとき向けたままの首の向きで、天井を見上げる。体の方は、かって知ったる部屋のドアを開けようと無意識にノブに手を伸ばし、まわし、扉を引き開け、廊下へ踏み出した。上に向いているままの視界をドアの鴨居が横切ったが、そのタイミングで足がつくはずの廊下の床は、はたして、なかった。
「なっ、んで!?」
足元を見ようと下を向くと、その勢いで前転をするような形になり、頭から落下すると知覚した瞬間に響の意識は途切れ、気がつくと、この場所で大の字になって、空を見上げていたのだった。
 その響の上に陰が落ちた。なにかと思って、焦点を空の向こうから手前へ引き戻す。すると、愛らしい女の子がのぞきこんでいた。まだ幼さがある、目が大きいかわいい顔。ピンクの上衣と色そろいの帽子に、襟まわりから肩にかけて紫の飾りが付き、胸元には淡いグリーンのリボンが結ばれていて、それはスカーフか、マフラーといった趣で背中に回され、背中側に流し下げられている。真上を見ている響の視界をからすると、彼女は響の脇に座り込んで、顔を見ていることがわかる。
その響の上に陰が落ちた。なにかと思って、焦点を空の向こうから手前へ引き戻す。すると、愛らしい女の子がのぞきこんでいた。まだ幼さがある、目が大きいかわいい顔。ピンクの上衣と色そろいの帽子に、襟まわりから肩にかけて紫の飾りが付き、胸元には淡いグリーンのリボンが結ばれていて、それはスカーフか、マフラーといった趣で背中に回され、背中側に流し下げられている。真上を見ている響の視界をからすると、彼女は響の脇に座り込んで、顔を見ていることがわかる。
「あなたが、ラナラナの機奏英雄サマですか?わたしはラナラナ。第2王女なの。もしかして『男』なの?お名前は?」
「僕は音羽響。呼ぶときは『キョウ』でいいよ。」
異世界に落っこちたか召喚され、お迎えは王女様。いよいよアニメかゲームの物語じみてきていた。
「ここはどこ?」
「ここは、ハルフェアっていう国。ラナラナね、胸騒ぎがしてここへ来てみたのょ。突然あたりが光に包まれて・・・あなたが空から・・・。
あなたはラナラナより大きいよね。だけど母さまほど大人じゃないし・・・キョウ姉さま?」
「男だから、姉さまじゃなくて兄さま。堅苦しいから、兄ちゃん、かな。」
「響、兄ちゃん・・・響兄ちゃん。ラナラナが『響兄ちゃん』て呼んだら、イヤ?」
「いや、いいよ。ところで『機奏英雄』って、なにかな?」
「指輪が光ってるでしょ。これが光るのは、歌姫になれる女の子と運命で結ばれてて、黄金の歌姫の歌で召喚された勇者が近づいたときなのょ。それにラナラナもドキドキしてるの!」
嬉しそうな様子で、女の子は響の顔の前に手をかざし、その指輪を見せた。逆光で陰になっている手に、確かに指輪が光っている。
「機奏英雄は、歌姫が応援して絶対奏甲で戦う英雄なのょ。それで悪い虫をやっつけて、アーカイアを救うんだょ。」
「ラナラナはハルフェアの王女さまなんだよね?今言った『アーカイア』?それは国なのかい?」
ラナラナは首を横に振った。
「ううん、ここはハルフェアっていう国なのょ。
『アーカイアに風の守護たるハルフェアの大島ありて。
風と水と陽に恵まれし人々住まう、天のかなめの地であれ。』
ソルジェリッタ姉さまに、覚えておきなさいって言われた言葉。姉さまは、ハルフェアを王女として治めてるのょ。」
「お姉さんは偉い人なんだね。じゃあ、ここはアーカイアという世界か大陸で、この中に『ハルフェア』っていう国があるんだね。」
「うん・・・、それでいいと思うょ。」
これはいよいよ『異世界ファンタジー』に飛び込んでしまったらしいと、響は思い始めた。それはある部分では正しかったが、現実は決してライトなストーリーにはならないことを、後に彼はその身をもって知ることになる。だが、ハルフェアの心地良い草原で、かわいらしい女の子を前にして、それを思わせる不吉の影はどこにも差してはいなかった。