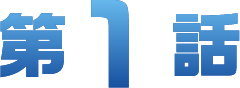第1話『勇者降臨!』
 南風に乗った潮の香りが鼻腔をくすぐる。葉の落ちはじめた木々は冬の気配を漂わせていたが、風にはどこかしら、夏の残り香が感じられた。
南風に乗った潮の香りが鼻腔をくすぐる。葉の落ちはじめた木々は冬の気配を漂わせていたが、風にはどこかしら、夏の残り香が感じられた。
海浜ドームの展望スペースから見下ろす海はどこまでも青くて、太陽の光を反射してきらきらと、まるで宝石箱をひっくり返したかのように輝いている。
どこかで、カモメが鳴く声がした。
ちぎれた雲が、海と同じように青い空を流れていく。
芹沢瞬兵は十二歳になったばかりで、この街の景色がとても好きだった。
宇宙開発事業団の拡張に伴って作られた海浜市は、二十一世紀の日本には珍しい新興の大都市である。
もともとはいくつかの小さな寂れた漁村だったものを、統合して超近代的な都市に仕立てたものだ。
干潟を極力温存する形で作られた街は鳥たちの楽園で、空と海のあわいが溶けあうその景色は、日々を鮮やかに彩ってくれていた。
『間もなく、VARS小学生部門、決勝戦の開始となります。関係者の方は、第三フィールドにお集まりください』
アナウンスのよく通る声が聞こえた。
「よしっ」
瞬兵は膝をぱんっ、と叩くと、足下に置いた工具箱を拾い上げ、気合をいれた。
戦いの時が来たのだ。
* * *
VAriable Robot System“VARS(可変型ロボットシステム)”は、瞬兵の年の離れた姉である芹沢愛美が開発した革新的なロボットトイである。
登録者の脳波と言語インプットの双方を読み取ることで、これまでのインターフェースとは比較にならないほど柔軟な情報入力を行える最新の超AIを搭載したVARSは、新世代のeスポーツとして爆発的な人気を博していた。
例えば、である。
これまでのロボットに「パンチを繰り出して相手のロボットを倒せ」という命令を与えるには、「相手との距離をセンサーで測距し当該位置に移動し」「右マニピュレーターでストレートを繰り出す」というような命令をコントローラで与える必要があった。無論、これでも単純化されたモデルであることは言うまでもないが、砕いて言えばこのようなことである。
VARSはそこに“脳波”という要素を加えることで、「行け!」「パンチだ!」程度のファジーな命令であっても正確に意図をくみ取り、実行するのである。
量子的な脳波観測だけでなく、AIのディープラーニングによって“言外の意図”を高精度で読み取ることもできるVARSが、軍事分野ではなく民生の、それも玩具分野から発売されたことは、世界の人々を驚かせた。
それは既に「子どものおもちゃ」の領域を超え、携帯電話(スマホ)に変わる新たなデバイスとなりつつあった。
が、瞬兵にとって大事なことは、VARSというロボットトイがメチャクチャ楽しい、ということである。
姉が作ったから、というだけの理由ではない。
自分が手塩にかけて組み立てた、全高15センチほどの人型のロボットが、レギュレーションの中で戦う! という奥深さである。
そこには、メカニックを組み立てるハードウェア的な面白さもあったし、AIを自分に合った形にカスタマイズするソフトウェア的な面白さもある。もちろん、VARSバトルにおける動作にはコントローラも使用するから、コンピュータ・ゲーム的な面白さもあった。
だから瞬兵は発売されるとすぐに寝る間も惜しんで夢中になった。
なんども失敗をして、なんども涙を流して、失敗と敗北を積み重ねて、そのたびに自分のVARSを強化し、操縦の技術を磨いてきた。
そうして、小学生部門の日本大会にのぼり詰めるまでになったのである。
最初は姉のコネではないかという陰口もあったが、瞬兵の鮮やかな戦いぶりは、そんな声をすぐになくしてしまった。
事実、これまでの準決勝までの戦いを、企業のeスポーツ・ワークスチームや高専の大人たち(瞬兵にとっては)が見てもくれて、何人かは中学を出たらこちらに来ないか、と誘ってもくれた。
そういう経験は、小学六年生の瞬兵にとっては大きな勲章になった。
(必ず、勝つぞ)
自分の手の中の青いVARSと、目があった――ような気がした。
もちろんそれは超小型のセンサーユニットがふたつ並んでいるに過ぎないのだが、人の形をしたロボットには、人のような心が宿っているのではないか、と思えた。
『VARS小学生部門、決勝戦を開始いたします。両者、VARSデッキへ』
(よし)
VARSデッキと呼ばれるプレイヤー席の前に、立つ。
めずらしく応援に来てくれたクラスメートの相羽菜々子が観客席で何やら叫んでいるのが見えたが、その言葉は聞こえない。
無視しているのではなく、それほどに集中しているのである。
瞬兵の視線の先にいるのは、奇しくも同じクラスの坂下洋。
どこか物憂げな瞳と、ガラス細工のように繊細な表情が特徴的な少年だ。
全国から集まってきた無数のVARSプレイヤーの頂点に立つふたりが同じ小学校の出身だというのは奇妙な運命である、としか言いようがなかったが、両者の実力を疑うものはいない。
それだけの戦い振りを示してきたからだ。
(手加減ナシだよ、瞬兵)
そう、洋の眼差しが告げていた。
(負けないよ、ヒロ)
その眼差しを、瞬兵は真っ向から受け止める。
両者がVARSを取り出し、スタートデッキに置く。
瞬兵のVARSは、空の色をしたブルーのマシン。
洋のVARSは、太陽の色をしたレッドのマシン。
好対照を成す二機のVARSは、造形としても作り込まれていて、観客たちの何人かから感嘆のため息が漏れた。
今日というこの日のために――
チューニングを重ね、トレーニングを積み上げてきた二機のVARS。
それは大人たちからみれば単なるオモチャであるかもしれないが、瞬兵と洋、ふたりの少年に取っては魂の分身である。
『VARS BATTLE FINAL! READY』
電光掲示板の前で、MCを務める女子高生、椎名ひろみが開始の合図をかける。
『GO!』
ひろみの手が振り下ろされる。
青と赤のマシンが、翔ける!
人のうごきそのままに、ふたつのVARSは真っ向からぶつかり合った。
VARSの戦いは、相手のマシンを破壊するというような乱暴なものではない。むしろ、そういう戦い方はルールで厳しく禁じられている。
今年の全国大会のルールはVARS専用武器を使用しないポイント奪取バトルである。
相手のマシンをフォールしたり、機体のあちこちに設置されたセンサーを叩いたりすることで、相手のポイントを奪うことができる。積極的な攻撃行動を一定時間取らないと、自身のポイントが減点される。
そうして、時間内に相手のポイントをゼロにするか、タイムアップ時にポイントで上回っていれば、勝ちになる。
アマチュア・ボクシングやレスリングの試合に、旧来のロボット競技の要素を加えたものだと思えばよい。
精妙なコントロールと先読み、そして機体のセッティングが鍵だ。
アクチュエータをパワー寄りにすれば、俊敏さが失われる。スピードを重視すると、機体の安定性が減少して倒されやすくなる。ポイント狙いの打撃戦と、一発逆転狙いのフォール戦はなかなか両立しない。
大人のプレイヤーたちでも、これらのバランスに解答を出せてはいないのである。大会が開かれるたびにセオリーが書き換わる、そんな新しいスポーツなのだ。
無論、瞬兵と洋のVARSはどちらも高いレベルでバランスが取れていることは言うまでもない。
その上で、瞬兵の青いVARSは近距離でのタックルの早さと安定性にパラメータを振った、いわば“グラップラー”である。
一方、洋の赤いVARSは距離を取ってのパンチとキックの正確さ、フットワークの精妙さにパラメータを振った、いわば“ストライカー”だ。
両者の戦いは、総合格闘技の試合にも似ている。
人間の肉体を模したロボット同士が戦う以上、一番理にかなっているのは、人間の戦い方であるからだ。
事実、瞬兵は動画サイトで格闘技の試合を何度も見て、その動きをAIに取り入れてもいる。
(人間が人間の肉体をコントロールする技術は、すごい!)
それが瞬兵の実感であった。
VARSを動かせば動かすほど、人型というフォルムの持つポテンシャルが、少年を感動させるのである。
青と赤のふたつのVARSは、まるでダンスでも踊っているように、フィールドの中央で絡み合い、もつれ合う。
すでに、両者のVARSは決勝大会までに疲労しているはずである。
だが、双方の動きにはいささかの乱れもない。
いや、むしろこれまでの戦いよりも鋭く、正確に動くようになっている。
これはVARSに搭載された超AIの学習精度を物語るものであり、操縦者の精神集中が極限まで高まっていることをあらわすものである。
限界ギリギリまで引き出された関節がスパークを上げ、フレームの軋みが聞こえてくる。
超低空から繰り出される赤いVARSの掌打は中国拳法の発勁を学習させたもので、位置エネルギーを運動エネルギーに転化させて衝撃力を高めたものだ。それを青いVARSは、柔術の達人がそうするように、なめらかにそらしてさばき、流れるように関節技に移ろうとする。その動きを、赤いVARSは宙返りで回避して見せる。
一切のよどみもなく、ためらいもなく、ふたつのマシンは、少年たちの信頼に応えて、動き続ける。
「すごいな、ホントに小学生なのか?」
「今の動きは、U-18チャンプのVARSより良かったんじゃないか?」
「純正品のパーツであんなに動けるものなのかよ」
そんな感嘆の声が、会場のそこかしこから聞こえる。
(スゴいよ! 洋のVARSはホントにすごい!)
その感嘆は、瞬兵も同じであった。
こう来るだろう、こう返してくるだろう、という予想の半分は当たる。だが、残りの半分は、さらに上を行って来るのである。
それが、楽しい。
もちろん、瞬兵も洋の上を行こうと、務める。
鋼鉄の拳がぶつかり合い、センサーとAIが互いの意図を捉えようと交錯する。
コントロールの瞬発力では、バスケットボール部でもある洋が上を行く。
だが、AIの教育レベルの高さは、毎日をVARSとともに過ごしている瞬兵がわずかにしのぐ。
総合的に見れば、両者の戦力には決定的な差はない。
天運――
疲労――
偶然――
そういうものが、勝負を決めるのだ。
熱い汗が、額を伝う。
集中力の限り、気力の限りを尽くして、瞬兵の言葉とコントローラとが、VARSに指示を出す。
互いの機体が青と赤の奔流になって、小さな、しかし巨大な旋風を巻き起こして、ぶつかり合う。
(いつまでも、つづけばいいのに)
それが瞬兵の偽らざる本音だった。
戦いの中で、さらにVARSのAIが成長していくのがわかる。洋の戦い振りを学習して、マシンがさらに強くなっていく。
それは洋の赤いVARSも同じことだ。
ふたりの少年と、ふたつのVARSは、高め合い、輝き合い、会場全体をどよめかせる。
互いのポイントが徐々に減少していく。
どんなささいなミスも、ふたりは見逃さない。
だが、そのミスも即座にリカバリーされるから、決定打にはならない。
そういう戦いだ。
激突する青と赤の機体は、少年たちの情熱の炎そのものだ。
渦となった炎は、海浜ドームそのものを飲み込んで、興奮のるつぼに変えていった。
* * *
同時刻。
地球をはるかに見下ろす漆黒の宇宙で――
「あれが……蒼き星……チキュウ……?」
青く輝く流星がひとつ、地球の月軌道上に現われた。その流星は地球の姿を認めたかのように、あたかも物思いに耽るがごとく、地球を観察するようなコースを取った。
が、刹那。
「!!!」
突如として出現した紅い流星が青い流星に襲い掛り、跳ね飛ばすようにして闇を切り裂き、地球へと向かうコースを取った。
ふたつの流星は螺旋を描くように、地球へと吸い込まれていく。それは人類が未だ理解し得ぬ霊的な質量を持たぬエネルギー体で、まっすぐに地球の一点を目指していた。
禍々しい真紅の輝きを放つ流星と、それに拮抗する神聖な輝きを放つ青い流星。
それはこれから始まる長い戦いを告げる、灯火だった。
* * *
そして、それは起きた。
激突する二機のVARSの中心で、ふたつの光が炸裂したのだ。
瞬兵の肉体は吹き飛ばされて、続いて、全身に強烈な衝撃が来た。
(え! なに……ボク……死ぬの……!?)
何が起きたのかわからなかった。
ただ、遠くにいくつもの悲鳴が聞こえて、ひどいことが起きていることは理解できた。
体中がひどく痛んで、指ひとつ動かすにも途方もない重さが感じられた。
このまま目を閉じていられたら、どれだけ楽だろうか。
安息に身を任せて、意識をなくしてしまえれば、どれほどいいだろうか。
細胞という細胞がそう訴えていた。
苦痛は重力の鎖になって、瞬兵の体を縛り上げていた。
だが、それでも。
瞬兵は、その幼い瞳を開こうとした。
この会場には、姉がいて、洋がいて、友達の菜々子がいる。
そうした大切なみんながどうなったのかを知らないままに、目を閉じることはできなかった。
だから、瞬兵は勇気を振り絞って、目を開こうとした。
そこにどんなにつらい現実が待っているとしても、知らないでいることはできなかった。
鉄のように重いまぶたを奮い起こし、水を吸った綿のように重い四肢を動かす。
そして。
瞬兵は見た。
(ひかり……!?)
爆炎の中、青い輝きが瞬兵たちを確かに守っていた。
その輝きは、青い龍のように見えた。
それが――瞬兵と“バーンガーン”の出会いであり――。
新たな「少年」と「勇者」の物語の始まりだった。
For the 21st Children……