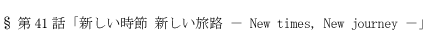
まぶしい日差しの下を帆船が滑るように進む。ひびきは甲板で、高い雲と、マストをかすめて飛ぶ鳥を見上げていた。磯の香りの風に乗って鳥が舞う。アーカイアの海も塩っ辛い海水である。彼女は、この船に乗るのにポザネオ港で磯の香りを感じて、初めてそれを意識した。
ひびきは、元の世界で船は乗ったことがなかった。彼女の世界は電車とバスでほぼカバーされていて、旅行で長距離列車や旅客機に乗ったことがあるだけだ。
船は馴染みのない交通手段だが、今乗っている大型の帆船であれば快適な旅をすごすことができそうで、船旅を気に入り始めていた。それでもポザネオ市での敗北は、まだ苦い経験だった。ツムギが去ったことを最後に意識を失ったひびきは、気づいてからのことを思い出した。
ひびきが目覚めたとき、そばにいたのはノイエンではなくクアリッタだった。ひびきはすこしの間があってから、彼女が飛行型の奏甲とともに伝令でやってきた瑠璃の歌姫だと思い出した。
ひびきは半身を起こして、座る姿勢をとった。
「おはようございます、ひびきさま。おかげんはどうですか?」
意識が戻ったことに気づいたクアリッタは、やさしく話しかけると共に、ひびきが目覚めるまでの経緯を語った。
ツムギが去るとほぼ同時に、ミリアルデ・ブリッツの奏座で気を失ったひびきは、まずはノイエンに助け出された。その2人へ、ポザネオ市の人々は白銀の暁の奏甲と戦ったことから味方と考え、救いの手を差し伸べてくれた。
別の英雄と歌姫に依頼して、奏甲でミリアルデを回収し、通常の動作ができるまでの修理を施す手配をしてくれたのは、クアリッタだと言う。
「黄金の工房の者が数人、本島へ渡る手段を探しに来ていました。その渡航手段を整えるのと引き換えに、奏甲の修理と改修をお願いするのは、彼らにしてみれば安い取り引きだったようですよ。
ミリアルデ・ブリッツは、すでに戦闘稼動が可能ですし、旅をするにあたって、外装も変えさせてさせていただきました。王家の華燭奏甲がそれとわかるままでは、すぐに噂となってしまうでしょうから。」
ひびきは、自分の奏甲に勝手をされたことに少しむっとした。だが、その怒りが表出するまえにクアリッタは言葉を続けて、ひびきを戸惑わせた。
「ひびきさま、あなたさまの行動を束縛する理由もありません。しばらくノイエンを歌姫として連れて、旅してはいかがでしょう?
ポザネオ市から本島へ渡るルートは、戦場の後をついていくようなもので、とても危険です。
工房の者たちに手配する船が、ポザネオ島の北の対岸へ向かいます。それに相乗りなされば、奏甲もつめますし、なにより安全です。
アーカイアであなたがなにをすべきか、すこし探してみてもよろしいのではありませんか、ひびきさま。」
クアリッタの言葉にひびきは、ソルジェリッタから離れ、ツムギにかなわず白銀の歌姫に会えないいま、自分の行き場がないことに、初めて気づいた。それなら、ここはどのようなところで、自分がここでどうするか、探すしかない。だが、疑問が1つあった。
「"ひびき"でいいです。ノイエンを行かせるのはどうして?ノイエンは、ポザネオ島の住人は、本島に渡っちゃダメだといわれてる、と言ってたわ。」
「状況がまったく違ってしまったからです。歌姫の能力がある人には、しなくてはならないことが、あまりにも山積しているのです。」
「ノイエンひとりが、そんなに大きなことなの?」
ひびきはいぶかしく思う。英雄の数だけ歌姫はいるはずだ。その多くの中から、わざわざクアリッタがノイエンを推薦する理由が見えない。
「ことが本島で起こっているからです。なにに尽力するかは、ノイエン自身が見つけて、決めるでしょう。」
ひびきはしばし無言で考えた。じっとしているのは彼女の性分ではない。白銀の暁と評議会が戦争をしている中で、どちらかの味方をするには、考える材料が乏しかった。
「ここが・・・アーカイアって世界が、どういうところなのか、もっと知る方法はない?」
「『叡智の殿堂』の図書館へ行けば・・・いえ、もうしわけありません。機奏英雄に、アーカイア文字はわかりませんね。
それならば、本島に渡ったところから、『隠者の洞窟』へ向かうとよいでしょう。隠者は、世界一の占い師ですから。ノイエンが案内できるでしょう。」
「わかりました。それならノイエンと行くわ。だけど・・・」
顔をしかめて言いよどんだひびきのあとを、クアリッタが続けた。
「英雄の奇声蟲化のことですね。」
「うん。」
「評議会は否定しています。黄金の歌姫から直々のお言葉ではありませんが、信じるしかないでしょう。」
「クアリッタは、疑ってるのね?」
クアリッタは、ひびきの言葉に目を鋭くして、ひびきの目を覗き込んだ。
「古代の詩歌の一節があのことで明らかになった、とわたくしは考えているだけです。
幻糸が何かしらの毒になるという記述を見たことがあります。ですが、私の知る"男がいない"アーカイアでは、誰の害にもなっていませんでした。だから信憑性を疑っていたのです。同時に記されている詩節ことも含めて。
ですが、奇声蟲化の対象は男でした。発病する『男性』がいて始めて、それは現実の現象として現れようとしています。ですが男性に対して『女性』英雄は、おそらく奇声蟲化しません。同じ詩篇に、そう記述されていた記憶があります。
私は紫月城へ行って、残された闇蒼の歌姫の蔵書から、これらの手がかりを探すつもりです。いつかあなたさまのお役に立てるかもしれませんし。
ひびき、ノイエンと行ってください。あなたの宿縁が、あなたのすべきことに導くでしょう。
歌がいつもあなたと共にありますように。」
クアリッタはそう言って、部屋を出て行った。しばらくしてノイエンがやってきて、大げさなくらいひびきの回復を喜んだ。
「ひびき、大丈夫?心配したんだから〜っ。よかったよかった!」
ベッドに座っているひびきに抱きついて、ひびきの背中を音がするほど手のひらでたたきながら、ノイエンは言った。
「宿縁でなくても、奏甲を通して調律してるとダメージとかキちゃうんだよ。赤い奏甲の槍を受けたとき、同じ場所がジンジンしたんだから!」
心配を態度で見せてくれるノイエンをうれしく感じつつも、ひびきは冷静に言った。
「ノイエン、ミリアルデを見せて。出発できるかどうか確認しなくちゃ。船が出るんでしょ?」
「クアリッタから聞いたのね。そうよ。あんまり時間ない。」
「それに間に合うように出かけなくちゃ。もう大丈夫だから、準備をしよ。
しばらく、一緒にいくことになるけど、よろしく、ノイエン。」
「こっちこそ。
それじゃ、工房の方に知らせてくる。どうせ整備してくれた人たちもその船に乗るから、船を下りるまで面倒みてもらっちゃおう。うんうん、それがいい。」
ひびきは1人になるとベッドを出て、脇のテーブルにまとめてたたんであった自分の衣類を見つけると、それに着替え始めた。下着から上着までがきれいにクリーニングされていた。電気が無く、全自動洗濯機もなく、クリーニング店だってないのに、どうやっているんだろう、とひびきは思った。
服を着て、胸元のリボンを締めたとき、すでにひびきに迷いはなかった。いまの目的地はとりあえずのものかもしれない。それでも動いていようと。