【第六昼 おっちゃんとウィンケル・ソース(前編)】
『狂王の城』の地下の大洞窟。腰巻きを着けたトロルが二人いた。
トロルとは身長三メートルの筋肉の塊で、岩のような肌を持っているモンスターだった。発達した筋力から繰り出される強力な一撃と、脅威の再生能力を持つ恐ろしい存在だ。トロルの眼は暗闇でも見えるので、は地下洞窟で活動するのでも問題なかった。
片方のトロルの名はおっちゃん。今年で三十二になるモンスターだった。もう一人は、若いトロルで名をボロルといった。
「ボロルはん。ちと、明日からしばらく留守にするから、他のトロルと組んで」
ボロルが怪訝な顔で尋ねる。
「予定表に外としか書いてなかったですけど、どこに行くんですか?」
「あっちこっちや。『狂王の城』でウィンケル・ソースを開発したやろう?」
ボロルはわけがわからない顔で尋ねる。
「ソースの開発とおっちゃんの外出って、何の関係があるんですか?」
「ウィンケル・ソースが売れておらんのや。だから、助っ人でソースを外で売ってくる」
ボロルが驚きも隠さずに尋ねる。
「ソースの販売って、それ、ダンジョン・モンスターの仕事ですか? 違うでしょう」
「わいもそう思う。せやけど、上からの命令やねん」
ボロルが渋い顔で、忌憚(きたん)なく意見を述べる。
「俺だったら、拒否したいなー。まったく仕事が違うでしょう」
「あんな、ボロルはん。仕事いうのはこんなこともせなきゃならんのか、と思うことでも、せなあかん時があるねん」
「でも、ダンジョン勤務でソースの販売はないですよ」
「せやねえ。でも、困っているから助けてくれと頼まれたら、冷たくしたらあかん。できる範囲で手伝ってやらな、あかんねん」
ボロルは頭に手をやり、納得しない顔をする。
「でも、なあ、俺には理解できないなあ」
「ダンジョン・モンスターは冒険者と戦うためにいるんやない。ダンジョンを存続させていくためにいるんや。せやから、わいはソースの販売かてやる」
ボロルが冴えない顔で送り出す。
「そこは、おっちゃんの人生哲学ですから、否定はしません。では、行ってらっしゃい」
おっちゃんは、一つだけ注意しておく。
「あと、新人さんと組むなら気を付けてな。怒るときはまず一拍おいて、冷静になってから叱らな駄目やで。感情で怒るのと、指導で叱るのは、違うで」
ボロルは気楽な顔で、軽く発言する。
「わかっていますよ。大丈夫ですよ」
翌日、ソース販売の担当になっている、オーガのガガーリの待つ厨房横の会議室に行く。
厨房横の会議室はトロルでも座れる椅子が十二脚あり、広い机が四つ、正方形に並んでいた。
オーガとは身長が二百五十㎝前後、赤い肌をして一本角を生やしおり、がっしりした体格の種族である。
オーガはトロルよりも力は劣るものの、強い力を持ち、暗闇でも見える目を持っている。
ガガーリは、革の半ズボンに革の半袖シャツを着ていた。
おっちゃんはいきなり営業に出るのではなく、事前にガガーリと打ち合わせを持っていた。
ガガーリが弱った顔で切り出す。
「この度は協力していただいて、ありがとうございます。ウィンケル・ソースですが、全く売れておらず、困っています」
「そうか。わいは、あの味は好きなんやけどな。揚げ物によく合う。目玉焼きに掛けても美味いやろう」
ガガーリが困った顔で内情を打ち明ける。
「事前の調査でも肉料理とよく合う、塩胡椒(しおこしょう)より美味(おい)しい――との評価でした。だが、これが、いまいち売れない」
「原因はわかっとるの?」
ガガーリが渋い顔をして告げる。
「わかっています。売れない原因は価格です」
理由に思い当たる節があった。
「ソースが美味しい理由は手間暇を掛けて、多種多様な材料を使うているからやからな」
「そうです。ここで下手に手を抜いたり、材料を減らせば、味が保てなくなる」
おっちゃんもガガーリの意見には賛成だった。
「手抜きは止めたほうがええで、安物で不味いと評価されれば、後から質を戻しても売れん」
ガガーリが頭を抱えて悩む。
「それはわかっています。でも、なら、どうしたらいいのか」
「ソースは何に入れて売っとる」
「もちろん、陶器の甕(かめ)に入れてですが?」
「よっしゃ。なら陶器の甕からガラス瓶に入れて、もっと高級感を出しつつ、少量で安く売ろう」
ガガーリが慌てて拒否した。
「ガラス瓶なんて、とんでもない。もっと価格が上がりますよ」
「ガラス瓶は買い上げて、洗って再利用すればええねん。そうすれば容器代かて浮く」
ガガーリの顔は否定的だった。
「でも、手間が掛かりますよ」
「売れない商品を持って、あっちこっちに行く手間も、ガラス瓶を回収する手間も変わらんやろう。なら、売り上げがあるぶんましや」
ガガーリの表情はどこまでも渋い。
「でも、回収に協力してくれるかな?」
「回収するガラス瓶の値段を高めに設定すればええ。場合によっては、ガラス瓶は業者から仕入れるより高く買うんや」
ガガーリが驚きも隠さずに拒否する。
「そんなの、ガラス瓶だけどこかで仕入れられたら、大損ですよ」
「帳面にどんだけの量を顧客が買ったかを記録しておいて、それ以上の瓶の買い取りは拒否すればええやん。販売データがあれば、大量購入や値引きにかて使えるやろう」
「でもなあ」とガガーリは渋った。
「まずは少量でもいいから、始めてみよう。それで駄目なら再考や。下手に後ろ向きな態度で策もなければ、販売員の士気も下がる」
ガガーリが冴えない表情で折れた。
「わかりました。少量からやってみますか」
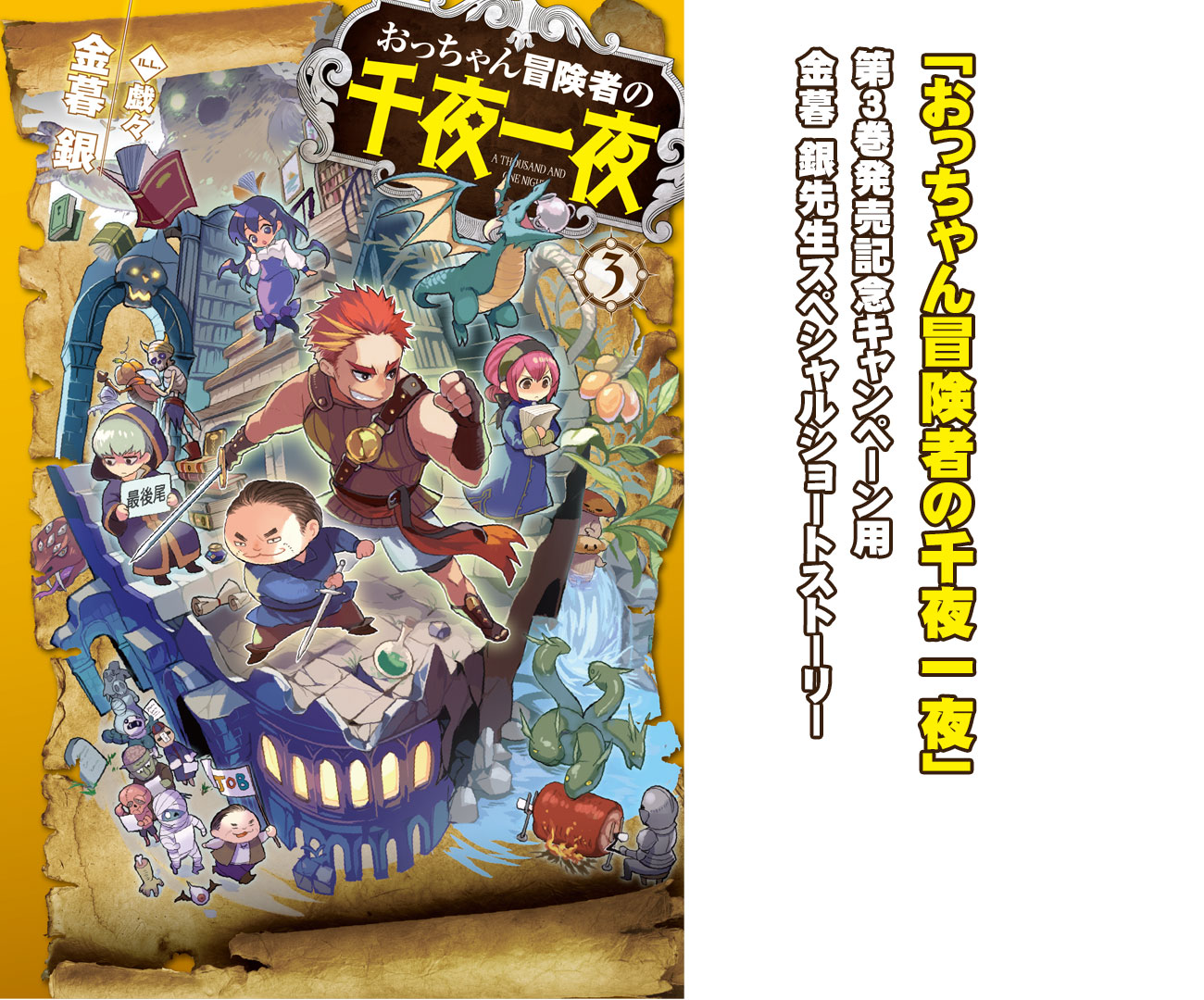
【第七昼 おっちゃんとウィンケル・ソース(後編)】
ガラス瓶に入れたウィンケル・ソースは売れた。
おっちゃんもソースを持って、村々を回ってソースを売り歩いた
ただ、売れたといっても馬鹿売れするほどではなかった。
ガラス瓶の回収費用を考えれば、十数%利益が増えただけだった。
ガガーリを交えての第二回の販売会議が行われ、ガガーリが渋い顔で告げる。
「ガラス瓶作戦は売り上げを伸ばしました。ですが、利益が思ったより伸びませんでした」
「最初から大売れを期待したらいかんよ。でも、わいも現場にソースを持っていってわかったけど、これは売れるで」
ガガーリが不思議そうな顔で尋ねる。
「なぜ、そう思うんですか?」
「村の男たちや子供たちに、人気が高いからや」
ガガーリが意外そうな顔で確認する。
「主婦層にではなくて、男たちに人気だから売れるんですか?」
「そうやで。村の奥さん方は、旦那さんや子供たちに美味しいもの食べさせたいと思うて、日々、苦心しとる」
ガガーリも穏やかな顔で同意する。
「そうでしょうね。私の妻も弁当には気を使っています」
「ウィンケル・ソースの最大の利点は揚げ物に合うことや」
ガガーリが明るい顔で認めた。
「確かに揚げ物には、私もウィンケル・ソースを使っていますよ」
「揚げ物が好きな男たちの間に、あれは美味いと伝わるのが大事や。揚げ物が嫌いな奥さん方かて、旦那や子供が喜ぶとわかれば、買ってくれる」
ガガーリが腕組みして、眉間に皺を寄せる。
「でも、どうやって、美味しいとわかってもらうかですね」
「作戦は二つや。一つは料理教室を開く。ソースの提供に関してはタダでもええやろう」
ガガーリは納得した顔で、おっちゃんの作戦を評価した。
「なるほど、料理を作らせて持って帰らせて、食べさせるわけですね」
「そうや。次は祭りや祭事に屋台を出店して、揚げ物を売るんや」
「こちらも、完成品を売るわけですか」
「口に入る直前まで、こっちでお膳立てする。それでこそ、ウィンケル・ソースは売れる」
「なるほど、そうかもしれませんね」
ガガーリは厨房係で都合のつく者には積極的に料理教室を頼んだ。
おっちゃんも屋台を引いて、目の前で揚げ物を作って、ウィンケル・ソースを掛けて売った。
料理教室は概(おおむ)ね盛況で、屋台も賑わった。ウィンケル・ソースの売り上げは伸びた。だが、やはり、爆発的には売れなかった。
第三回の販売会議が行われ、ガガーリが複雑な顔で残念がる。
「依然と比べれば格段に売れています。販売員の士気も上がりました。でも、作っているほうとしては、もう一押し、ほしいところです」
「それについては、実は案がある。ウィンケル・ソースを使った商品を開発する」
ガガーリが興味を示した顔で訊く。
「どんな商品ですか?」
「難しいものやない。揚げ物にウィンケル・ソースを掛けて、パンに挟んだものや」
ガガーリが、がっかりした表情で教える。
「それなら、すでにカツサンドとして売られていますよ」
「ちゃうねん、挟むのは肉やない。魚介の揚げ物や」
「なぜ、魚介ですか?」
「肉の脂は冷めると不味くなる。だから、魚介や。さらに、使用する油も融点が低く、冷めても味がそれほど下がらん植物油を使う」
ガガーリの表情が和らぐ。
「冷めても味が悪くなりにくい揚げ物にウィンケル・ソースを掛ける。それをパンに挟むんですね」
「ウィンケル・ブレッドとでも名づけて売ればええ」
ガガーリが俄然と興味を示して訊く。
「具材となる具はどうします? 海老とか鯛を使いますか?」
「高級食材は使わんくてええ、また、単価を下げるために野菜も加える。つまり、掻き揚げや」
ガガーリの顔が段々と明るくなる。
「なるほど。ウィンケル・ソースを使った掻き揚げサンドをウィンケル・ブレッドとして売るんですか。行けるかもしれませんねえ」
「そうや。ウィンケル・ブレッドなら昼飯にかて喰える」
ガガーリが自信に満ちた態度で発言する。
「いいでしょう。ウィンケル・ブレッドを開発しましょう」
『狂王の城』で、ウィンケル・ブレッドは開発された。
ウィンケル・ブレッドは、普通のパンに挟む代わりに、クロワッサン生地を使用して掻き揚げを包んだ以外は、おっちゃんの案どおりだった。
ウィンケル・ブレッドは広まり、各種の亜種が生まれ、『狂王の城』の周りでは、さも昔からあるように食べられた。
ウィンケル・ブレッドの広まりと共に、ウィンケル・ソースも広まった。
【第八昼 おっちゃんと盗まれた宝】
ウィンケル・ソースの販売から戻って来て、おっちゃんは再び地下空洞の仕事に戻った。
久々にダンジョン勤務に戻ると、ボロルが安堵した顔でやって来る。
「おっちゃん、よく、ご無事で戻って来てくれました。ほっとしました」
「ソース売りの仕事やからね。危険は一切ないから無事やで」
ボロルが苦い顔でぼやく。
「もう、こっちは大変でしたよ。使えない新人で、危うく一緒に心中するところでした」
「そうか、それは大変やな。そんで、何か変わったこととかあった?」
ボロルが得意気な顔で、ニュースを語る。
「ありましたよ。ここ最近、特定の場所にだけある宝が、冒険者に何度も持っていかれているんです」
「宝の流出か? それは頭が痛いのう」
ボロルが渋い顔で教えてくれた。
「しかも、どうやら、同じ冒険者にやられているって話ですよ」
「それは、あかんわ。対策を立てんと冒険者に舐められる」
おっちゃんは、その日の勤務が終わると、フロア・ボスに呼ばれた。
大空洞のフロア・ボスは『トロル・キャプテン』のドドンである。
『トロル。キャプテン』は、トロルの中でも特段に戦闘能力に長(た)けたトロルに付けられる呼称である。
ドドンは四十代のトロルで、革の鎧を着て、愛用の両手用のハンマーを持っている。
おっちゃんは、一辺が五メートルほどの秘密の小部屋で、ドドンと会った。
いつも数人のお供を連れているドドンは、一人だった。ドドンは難しい顔をして相談する。
「おっちゃん、宝の流出の話は聞いているか?」
「へえ、噂には聞いておりますけど」
ドドンが険しい顔で声を顰(ひそ)めて、内情を話す。
「宝の流出だが、誰にも気付かれずに、宝を何度も持って行くなんて、どうも手際が良すぎる。宝物係ではダンジョン・モンスターの仕業だろう、との話も出ている」
「それは、まずいですわ。宝を守らなければあかんダンジョン・モンスターが、宝を持ち出していたら、懲戒ものでっせ」
ドドンが辺りを気にしながら依頼する。
「そこでだ。悪いが、本当にダンジョン・モンスターによる犯行か調べてほしい」
「仲間を疑う仕事はあまりやりたないですな」
ドドンは困惑した顔でお願いする。
「そう断らないでくれ。頼むよ。もし、他のトロルの犯罪なら、何とか上にばれる前に内々で処理したい。それが、他のトロルを守ることにもなる」
(ドドンはんはフロア・ボスや。せやけど、トロルの一族の名門出身やから、種族の評判を落としたくないんやろうな)
「気が進みませんけど、やってみますわ」
おっちゃんは翌日にシフトを外れる。
問題の宝のある部屋で、『透明』の魔法で隠れて、宝物を見張った。補充係がやって来て中身のない状況を確認して、宝を補充する。
(ここまでは、問題ないのう)
宝が補充されて三十分で、厚手の茶の服を着た若い男の冒険者が、足取りも軽やかに、やって来る。
(冒険者が来おったで、見たところ一人のようやな。あいつが犯人か)
冒険者はおっちゃんに気付かない。冒険者は宝箱の罠を簡単に外し、中身を抜き取って素早く移動を開始する。
おっちゃんは冒険者を尾行するが、途中で見失った。
(見失ったか。敵ながら、見事な侵入と撤退やな)
その日は早く上がって、大空洞の地図とモンスターの巡回経路、宝の補充時間を検討する。
だが、誰にも見つからずに大空洞に侵入して、出て行くルートが見つけられなかった。
(なるほど。これで、宝物係の連中はモンスターの仕業やと睨んだわけやな。でも、犯人は冒険者やった)
おっちゃんは次の日、宝物係に頼んで、宝物を素焼きの壺に入った香水に替えてもらった。
おっちゃんが再び、『透明』の魔法で隠れていると昨日の冒険者がやってくる。
冒険者は素焼きの壺を見て、首を傾げる。だが、高価な品なので持ち帰った。
おっちゃんは顔だけ狼に変えて素焼きの壺から漏れ出る匂いを追跡する。
(匂いが漏れていることに気付いておらんようやな。今度は見失わないで)
すると、匂いが壁の前で消えていた。壁を調べると、床面の近くに縦五十㎝、横三十㎝の穴が開いていた
壁の向こう側に遠回りして行く。同じような大きさの穴があり、匂いが微かに残っていた。
おっちゃんは地面に顔を付けて覗く。だが、向こう側が見えない。
「まさか、この穴、向こうとこっちで、繋がっておるんか」
おっちゃんは蛇の姿を念じ、姿を蛇に変えた。
いつもはトロルの姿をしているおっちゃんだが、正体はトロルではない。本当は、姿形を自由に変えられる、『シェイプ・シフター』と呼ばれるモンスターだった。
蛇の姿になったおっちゃんは穴の中を進む。穴は蛇行していたが、確かに壁の向こう側に通じていた。
入ってきた場所に戻って、腰巻きを装備する。
私室で地図とシフト表を確認する。大空洞から宝の場所まで、誰にも遭わずに移動できる安全な経路があった。
今度は通路の穴の側に隠れていると、冒険者がやって来る。冒険者が関節を外して穴に入るところを目撃した。
人間による犯行が確認できたので、おっちゃんはドドンに報告する。
「関節を外して、壁の中にできた隙間を蛇のようにして進める人間が犯人でした」
ドドンは真剣な表情で語る。
「犯人は人間だったか。さっそく罠を張って、捕まえよう」
「ただ、その経路を利用するにしても、こちらの配置と勤務時間のシフトを知っておらんと、不可能な犯行ですわ」
ドドンの表情が曇る。
「内通者がいると予想するのか?」
「内通かどうかは、知りまへん。せやけど、禁止されているダンジョン内へのシフト表の持ち込みを誰かがしておる状況は確かですわ」
ドドンが真摯(しんし)な顔で請け合った。
「わかった。そっちも、すぐにシフト表の持ち込みの禁止を徹底する」
ドドンに情報を伝えて翌日、全身の関節を自由に外せる冒険者が罠に掛かって死んだ、との情報が流れた。
またシフト表の持ち込み禁止の徹底の通達も出た。以来、同一の冒険者による宝の連続の持ち出しの記録は止まった。
【第九昼 おっちゃんと陰謀の予感】
おっちゃんはボロルと一緒に地下空洞の部屋で待機していた。
部屋は広さが八十平方メートル、高さが六メートルで、岩盤を刳り貫いて作った部屋だった。部屋には北側、西側、東側に通路がある。
西側の通路から十以上の足音が聞こえてきた。
おっちゃんは、すぐにボロルに指示を出す。
「まずい! 人間が大勢、来おった。逃げるでボロルはん」
おっちゃんはボロルと一緒に、避難用の東側通路に入って、隠しスイッチを押す。
緊急遮断用の岩壁が、東側通路と部屋とを繋ぐ境の通路に下りた。 下りた岩壁は冒険者がいる側からは操作できないので、安全である。
ボロルがさらに人間の侵入を知らせるスイッチを押した。おっちゃんたちのいる場所では警報は響かないが、これで他の場所にいるモンスターには警告が行く。
おっちゃんは岩壁に耳を付けて、向こう側の音を拾っていた。
冒険者たちの足音は、おっちゃんたちがいた部屋の中で停まって、すぐに移動しなかった
(何や? 向こうで作業しておるの?)
冒険者は五分ほどで、おっちゃんとボロルがいた場所から立ち去った。
ボロルが心配した顔をして、小声で尋ねる。
「冒険者のやつら、行きましたか?」
「いや、油断は禁物や。またすぐに戻って来るかもしれん。さすがに、十人以上を二人で相手にする決断は、無謀や」
ボロルが訝(いぶか)しむ表情で質問する。
「でも、十人以上なら、二パーティーですよ。冒険者が連携して、何をするつもりでしょう?」
「地下空洞を本気で攻略に来たのかもしれんな。きっと別の場所に冒険者は、まだうじゃうじゃいるかもしれん」
ボロルが冴えない顔で心配する
「フロア・ボスのドドンさん、大丈夫かな?」
「本気になった人間は、危険やからなあ」
おっちゃんの予想通りに、五分程度で足音が戻ってきた。それから足音は二手に分かれる。
一つは部屋に残り、もう一パーティーは、部屋からの別の通路に進んだ。
おっちゃんたちが守っている部屋の先には別の部屋がある。部屋にはドドンの部屋の鍵と、宝が入った二つの箱がある。
通常はどちらか一つしか取れない仕組みになっている。でも、二パーティーで同時に来た場合のみ、両方とも取れる。
「おかしいで。二つのパーティーがいれば、宝も鍵も両方とも持っていける。なのに、片方しか持っていかんつもりや」
ボロルが真剣な顔で提案する。
「どうします、今なら、各個撃破できるかもしれませんよ。撃って出ますか?」
「いや、やめとこう。戦闘中に残りに奴らに戻って来られたら、挟み撃ちに遭う」
部屋から出ていった冒険者の足音が五分で戻ってきた。なので、冒険者たちは合流した状況が知れた。
次に十分以上してから、足音は部屋から出て行った。
おっちゃんたちは、すぐに出ていかなかった。さらに、十分以上の時間を置いてから、岩壁を上げて部屋に戻った。
部屋に戻ると、本来なら北側の通路の先の部屋にあるはずの宝箱があった。
「あれ? 冒険者が宝箱を置いていっている?」
ボロルが近づこうとしたので、注意する。
「不用意に近づいたら、あかん。何が仕掛けてあるかわからん。危険物処理班に連絡や」
「わかりました、俺が連絡してきます」
おっちゃんは用心のために、東側通路に戻って、危険物処理班を待つ。
連絡を入れたが、すぐに危険物処理班が来なかった。
ボロルが不機嫌な顔で愚痴る。
「遅いですね、危険物処理班」
「冒険者は同じような箱を地下空洞のあちらこちらに置いてあるな」
ボロルが驚いた顔で質問する。
「何で、そんな真似をするんです? 普段、トラップにやられている仕返しですか?」
「そんな動機ならええが、これは何か、嫌な予感がするで」
「俺は嫌がらせとしか思えないけどなあ」
用心しながら待つと、危険物処理班のオーガが、不機嫌な顔でやってくる。
オーガが苦い顔でぼやく。
「人間のやつら、ここにも宝箱を置いていったのか」
「何や? やっぱり冒険者はいたるところに宝箱を設置していったんか?」
オーガがうんざりした顔で告げる。
「そうだよ。中身は空で罠だけ仕掛けてあるんだ」
「どんな罠や? 爆発系? それとも、毒ガス系?」
オーガはむっとした顔で教えてくれた。
「それが、大きな音が出る警報系なんだよ」
ボロルが不思議そうな顔で、オーガに尋ねる。
「冒険者がダンジョンに警報機なんか仕掛けて、意味があるんですか?」
「俺はないと思う。ただ、解除するのはやたら難しくて、もう、いくつか作動させちまったものがある」
ボロルが興味のある顔で質問する。
「作動させると、冒険者が戻って来るんですか?」
オーガが呆れた顔で説明する。
「来ないよ。壊れるまで音が鳴っているだけだよ」
ボロルが困惑した顔で意見を口にする。
「人間のやることは、わけがわからないですね」
「わからんで。人間は音の反響を利用して、地下空洞の地質や、その上の建物の構造を、調べているのかもしれん」
おっちゃんの言葉に、ボロルが驚きの表情を浮かべる。
「そんな真似、可能なんですか?」
「冒険者なら平面の地図で足りる。それに、冒険者は足で地図を作るから、そんな面倒臭い真似はしない。もしかしたら、これは何か大きな事件の前触れかもしれんのう」
第十昼 おっちゃんと攻城戦(前編)
おっちゃんはいつものように地下空洞で、ボロルと一緒にいた。
ボロルが暇そうな顔で告げる。
「何か、ここ二週間くらい、めっきり冒険者が来なくなった気がしませんか?」
「そうやねえ。年末年始でもないのに珍しいのう。でも、そんな時もあるやろう」
誰かが走って来る音がして、ボロルが身構える。
おっちゃんは足音で、相手がトロルだとわかっていたので、構えていなかった。
新人トロルが緊迫した顔で告げる。
「大変です。人間です。人間が軍隊で攻めてきました」
ボロルは驚きを隠さない。
「軍隊を使って、ダンジョンを大勢で攻略しようとしているのか?」
おっちゃんは、それほど驚かなかった。
「前回、音を使って地質や上部の城の構造を調べておったからな。戦争を仕掛けてくるんやないかとは、思うとった」
ボロルが慌てふためいて意見する。
「何を呑気に構えているんですか! 万なんて単位の人間には、対処しきれませんよ」
「まともに対処したらできん。でも、人間が軍隊を出してくるなら、こっちかて、馬鹿正直に付き合ってやる必要やない。入口を閉鎖したらええ」
ボロルが浮かない顔で質問する。
「人間相手に篭城戦をやるんですか?」
「作戦はダンジョン・マスターのウィンケル卿が決めることやから、わからん。せやけど、これは、もうダンジョン対冒険者やない。戦争や」
ボロルが渋い顔で零(こぼ)す。
「戦争って俺、経験はないな」
「人間を相手にしとれば、いつかはこういう事態にもなる。お互い無事に生き延びようや」
翌日、おっちゃんはダンジョン勤務を解かれ、投石部隊に変更になる。
『狂王の城』は円形の城で、高さが五十メートル、周囲は二十キロメートルにも及ぶ巨大な城である。城は二重の城壁で覆われていて、堅固なものだった。
おっちゃんたち投石部隊は高さ二十メートル、厚さ十五メートルの城壁の上に配備された。
城壁から向こうには、すでに人間の部隊が布陣を終えていた。人間側は城の正面に戦力を集中させていた。
「これは、壮観やなあ。二万はおるなあ」
投石紐による投石部隊に一緒に配置されたボロルが、ぼやく。
「そんな感心している場合ですか。それに、武器が何で石なんですか? 弓矢のほうが、よくないですか」
「何や? ボロルはん、弓矢が得意なん?」
ボロルが暗い表情で吐露する。
「使ったことないですけど」
「弓矢って、慣れんと難しいんやで。それなら、石かて変わらんやろう」
「でも、こんな小さな石じゃ、当たっても人間は死なないでしょう」
「普通の石なら、死なんな。でも、これ、小さいけど爆発する石やで」
銅鑼(どら)が鳴らされる音が、聞こえてきた。盾を持った部隊を先頭に人間たちが進軍を開始した。『狂王の城』と人間軍隊の間で投石機による応酬が始まる。投石機どうしの応酬の間をぬって人間の攻城部隊と支援する弓矢部隊が進んでくる。
『狂王の城』からも攻城部隊を近づけさせまいと、矢を射かける。
双方の矢が飛び交う中、三角屋根に囲まれた破城槌がゆっくりと迫ってくる。
指揮官トロルの声がする。
「投石紐部隊構え。目標、敵の破城槌。投石開始」
おっちゃんたちが投石紐により石を投げる。石は破城槌に命中する。石は破城槌の屋根に当たって弾かれるが、数秒後に爆発が起きる。
だが、破城槌は多少の衝撃などは計算に入れて設計されているのか、簡単には壊れない。そうこうしているうちに破城槌が正門に到着して門に丸太を打ちつけ始める。
破城槌が二機、三機と城の正門に辿り着くと、ラッパが鳴る。
「後退の合図や」
おっちゃんたち城壁の上で戦っていた部隊が、二番目の城壁へと掛かる板を伝って、後退する。
後退を終えたタイミングで、破城槌が一番目の門を破ってきた。また敵の歩兵も次々と一番目の城壁に上がってくる。
二番目の城壁に敵が侵入してこないように掛かっていた板が、落とされた。
人間の歩兵がわらわらと一番目の城壁の上に上がってきて、一番目の城壁が落ちたように見えた。
破城槌も二番目の門を攻略しようと進軍する。
地面が崩落した。落とし穴に嵌った破城槌に、火の着いた油壺が投下される。落とし穴の底にあった油に着火して、たちまち燃え上がる。
破城槌の進軍が止まった。一番目の城壁の上った攻城部隊が、ロープを渡して二番目の城壁に渡ろうとした。
だが、突如として足場になっている一番目の城壁が崩落した。城壁の上に乗っていた部隊と壁際の部隊が、崩落に飲み込まれて全滅する。
人間側は部隊の再編成と再攻勢を試みる。再編成された部隊は、崩れた一番目の壁の残骸を乗り越えて、二番目の城壁を登ろうとした。
今度は崩落した瓦礫が空中に浮いて、人型に集まる。瓦礫は身長三メートルのロック・ゴーレムに次々と変わる。ロック・ゴーレムは、壁に近づいてきた攻城部隊と白兵戦を繰り広げる。
ロック・ゴーレムと戦っていると、二番目の城壁の上から爆発する石や矢が人間を目掛けて飛んでいく。
城壁の残骸が全てロック・ゴーレムに変わると、危険と判断したのか、人間側は一度、攻城を諦めて退却する。
攻城戦初日は、ウィンケル卿側に死者はほとんどなく、人間側は破城槌三機と攻城部隊の一割を失った。
【第十一昼 おっちゃんと攻城戦(後編)】
その夜は曇っており、月も星も、出ていなかった。また、人間側の陣地に向かって良い風が吹いていた。
おっちゃんたちは夜の闇に紛れて城の上で全長三十mのカタパルトを組み立てる作業をしていた。
カタパルトが組み上がったので、ボロルと一緒に休憩を摂る。
一緒に作業をしていたボロルの顔には、ありありと不満が出ていた。
「城の上でカタパルトを組み上げたところで、人間の陣地まで攻撃が届くとは思えないんだけどな」
おっちゃんは作業をしながら、軽い調子で口にする。
「ま、矢や石なら、届かんやろうな」
ボロルが興味を示した顔で尋ねる。
「石や矢を飛ばさない? おっちゃんはこのカタパルトが何をするためのものか、わかっているんですか?」
「これは、グライダーを装備した種族を打ち出すためのカタパルトや」
ボロルが驚いた顔で意見する。
「空から夜襲を懸けるんですか?」
「ほれ。向こうを見てみい。コボルドの集団がいるやろう」
コボルドは犬のような顔を持つ種族で、身長は一メートル五十センチほどと低く、体重も四十キロ程度と、あまり大きくない。そのコボルドが五十人あまり、集団でグライダーを準備していた。
ボロルが顔を歪め、否定的な意見を述べる。
「コボルドにグライダーを装備させてカタパルトから打ち出せば、それは人間の陣地の上に届くでしょうよ。でも、コボルドはコボルドですよ。すぐに鎮圧されますよ」
おっちゃんはボロルとは意見が違った。
「それは、ボロルはんがコボルドを甘く見てるからや。彼らは、単なるコボルドやない。コボルドの精鋭、コボルド空挺部隊や」
ボロルが首を傾げて質問する。
「空挺部隊って、何ですか?」
「空から相手の側面や背後に回り、奇襲する部隊や」
ボロルが驚いた。
「うちに、そんなの、あったんですか?」
ボロルの反応は無理もなかった。
全てのダンジョン・モンスターが、他の部署のモンスターを知っているわけではない。まして、他の部署にあまり興味を示さないボロルなら、なおさらだった。
おっちゃんは滔々(とうとう)と語る。
「あるで、空挺部隊。コボルドはダンジョンの中では、トロルに劣るやろう。せやけど、こういう場面では、大きな力を発揮するんや」
ボロルが渋い顔で疑問を口にする。
「でも、どうせ空から攻撃するなら、ドラゴンのほうがよくありませんか。うちのダンジョンにもいますよね、ドラゴン」
「ドラゴンは大きいから、目立つ。ドラゴンによる襲撃は人間も読んどる。だから当然、対策も立てたあるやろう」
ボロルはどこまでもコボルド空挺部隊に否定的だった。
「でも、俺たちの半分しかないコボルドに、それほどの戦果が認められるかな」
「それを言うたら、冒険者かて、わいらより小さいで。でも、トロルを上回る戦闘能力がある奴は、おるやろう」
ボロルは明らかにコボルドを馬鹿にしていた。
「でもなあ、コボルドはコボルドですよ」
「まあ、見ていたらええ。夜明け前には、ボロルはんの考えは変わっとる」
準備ができると、十列に設置されたカタパルトにコボルドが黒いグライダーを装備して配置に着く。
おっちゃんたちはコボルドの合図で、大きなバネのような発射装置を全力で引く。
引き絞られたバネ板がレバーを押すことで自由になり、グライダーを装備したコボルドが空に飛んでいく。
風に乗ったグライダーは、どんどんと上昇して小さくなる。グライダーに掛けられた魔法が発動して透明になる。
五十人からなる空挺部隊が、夜の闇に消える。
おっちゃんとボロルはその晩は夜間警備の仕事があったので、しばらく見張りに立つ。
一時間、二時間と時間が経つが、人間側の陣地に変化はない。
ボロルが眠そうな顔で愚痴る
「何も起きませんよ。コボルド空挺部隊は失敗したんですかね?」
「夜明け前の一番暗い時間帯を狙って、行動を起こすんやろう。まあ、見てて、わいの勘やと、もうすぐ、事件が起きるで」
ボロルがコボルドを馬鹿にして発言する。
「そうかなあ。コボルドには荷が重い任務だったんだと思うんだけどなあ」
「ほら、始まったで」
おっちゃんが人間の陣地を指差すと、人間の陣地の一角から煙が上がっていた。
ボロルが目を大きく見開く。
「人間の陣地の一箇所から煙が上がっていますね。まだ、朝飯には早いよなあ」
「煮炊きの煙なら、もっと広範囲に上がる。あれは焼き打ちの煙や」
ボロルが首を傾げる。
「あれ? でも、煙が上がっている場所は一箇所ですよ。焼き討ちなら、もっと派手にあちこちから火の手が上がらないと意味ないんじゃ」
「あれでいいねん。人間たちを焼き殺すのが目的やない。コボルド空挺部隊のターゲットは、敵の兵糧倉や」
火は朝まで燃え続けた。昼には「人間側の兵糧の焼き討ちに成功した」との一報が現場にもたらされた。
【第十二昼 おっちゃんと食糧の奪い合い】
ダンジョンである『狂王の城』が普通の城と違うところがあるとすると、何か。それは、多数の秘密の出入口を持っている点である。
今も、人間たちに気付かれないように、トロルの集団がダンジョンから出てきた。
革鎧と投石紐で武装したボロルが、興奮した様子で話す。
「いよいよ、俺たちも、戦場に投入されるんですね。これで手柄を挙げれば、出世ですかね」
「そうやね。うまく行けば褒美は出るやろうな」
ボロルが威勢もよく宣言する。
「人間の奴らに、俺たちの力を見せ付けてやりましょう」
「ボロルはん。わいらがどこに向かうか知っとるの?」
ボロルが、きょとんとした顔で返事をする。
「どこって、戦場でしょう? 人間たちと正面決戦ですよ」
「わいはそうは思わん。ウィンケル卿は人間の部隊との正面決戦は避けると思うで」
ボロルは納得がいかない顔で申し立てる。
「どうしてですか? 奴らを倒さないと、ダンジョンは元通りに運営できないでしょう」
「そんなことないで。人間を撤退させれば、こっちの勝ちや」
ボロルは訳がわからない顔をしていた。
おっちゃんたち五十名のトロルが着いたのは、オーガの村だった。
立派な体の四十代の男性村長のオーガが、隊長のドドンを食糧庫に案内する。
「指示された通りに、麦を纏めておきました」
食糧庫には厳重に包装された麦が百二十キロ入りの俵で百俵あった。担ぎ紐も置いてあった。
トロルの一人が小さな笛を吹くと、担ぎ紐がきゅっと締まる。
ドドンが満足そうな顔で頷く。
「よし、魔法の担ぎ紐はきちんと動作するようだ」
ドドンが真剣な顔で、村長に確認する。
「女子供の避難は済んでいるんだな」
村長が神妙な顔で頷く。
「村には男衆しかいません」
ドドンが厳しい顔で念を押す。
「村にある食糧はここにある麦だけだな?」
村長は神妙な顔のまま頷く。
「他の食糧と食料は全て持ち出しました。麦以外は村に残していません」
「よし、わかった。では、手筈どおりに、人間が襲撃してきたら、麦の入った俵を置いて逃げてくれ」
準備の確認が終わると、おっちゃんたちは村と人間の陣地を繋ぐ森に待機する。
ボロルが不思議がって、おっちゃんに尋ねる。
「おっちゃんさん、村を防衛しなくていいんですか?」
「ええねん。人間に略奪させたらええ」
ボロルがむっとした顔で意見する。
「でも、せっかく兵糧倉を焼いたのに、ここで略奪させたら意味ないでしょう」
「兵糧庫を焼かれた人間は、きっと、近くのモンスターの村から略奪をする」
「それは、襲うでしょうね」
「略奪を成功させて、足が遅くなった部隊をうちらが襲うんや」
ボロルが不満気に語る。
「でも、たかが百二十キロでしょう? 軽々と持てますよ」
「人間はトロルと違う。百二十キロも背負えば身軽に動けん。そこを石で滅多打ちにする」
石といっても、殺傷力は馬鹿にならない。ましてや、トロルの豪腕から繰り出される石なら、当たり所が悪ければ、即死も有り得る。
森に隠れていると、百名ほどの人間の部隊が通り過ぎる。
おっちゃんたちは行きの部隊を見送る。しばらくすると、人間たちの足音が戻ってきた。
ドドンが険しい顔で、「攻撃開始!」と指示する。トロルが魔法の担ぎ紐を締める笛を吹く。
おっちゃんたち投石部隊が飛び出して、投石を開始する、
次々に飛んで行く石飛礫(いしつぶて)に、人間たちは倒れて行く。
人間は担でいる麦を捨て、応戦しようとした。だが、魔法の担ぎ紐が体を締め付けて、思うように外れない。
また、短剣で切ろうにも、ワイヤーが編み込んであるので、簡単には切れない。おっちゃんたち投石部隊は後退をしながら、投石を続けて人間たちを倒してゆく。
その間に近接戦闘部隊が敵の背後と側面に出現する。人間たちは重い麦を背負おったまま、進むも引くもできずに全滅した。
人間を全滅させたおっちゃんたちは麦と担ぎ紐を回収する。
トロルの筋力であれば、担がずとも両手で余裕で麦を持てた。麦を倉庫に戻すと、道端に転がる死体を隠して、次の犠牲者を待つ。
日を改めて、人間の略奪部隊はもう一度やってきたが、同じ方法で倒された。
数日待って、人間が来なくなったので、おっちゃんたちは麦を持って『狂王の城』に帰還した。
『狂王の城』で休んでいると、ボロルが気の良い顔で戦果を誇る。
「人間たちは結局、麦をほとんど持ち帰れず、やられたそうですよ」
「他の村の様子はどうや?」
ボロルが、にこにこした顔で語る。
「坂道から丸太を転がしたり、渡河の最中に水中から襲ったり、馬を興奮させて荷馬車を潰したり、と、他の部隊も食糧と食料をほとんど渡さなかったそうです」
「焼き討ちで兵糧は少なくなった。近くのモンスターの村からは略奪もできん。これで、人間は兵糧を後方の街から運ぶしか、なくなった」
ボロルが浮き浮きした顔で語る。
「これで、あとは補給線を攪乱してやれば、人間は城責めどころではなくなりますね」
「そうやな。ウィンケル卿の狙い通りに、作戦は運んどるのう」
【第十三昼 おっちゃんと兵糧の買い占め】
ドドン指揮の元、百名からなるトロル部隊は、秘密の出入口から次なる作戦を実行するために出撃する。
おっちゃんたちは人間の街から人間の陣地へと続く道の脇にある森に潜伏する。
ドドンから作戦の説明がある。
「これより、合図をしたら、人間の輜重部隊を襲う。だが、成功はしなくてもいい。笛の合図があったら、速やかに撤退せよ」
作戦説明のあと、一緒に配属されたボロルが困惑した顔で、おっちゃんに尋ねる。
「成功しなくて良いなんて、そんなんで、いいんですかね?」
「ええんやないの。それが作戦やから」
ボロルは不満そうだった。
「失敗してもいい作戦なんて、あるんですか?」
「失敗してもいい作戦はない。だが、輜重部隊の襲撃はこの作戦の本来の目的やない」
「どういう意味ですか?」
「静かにしいや。人間が傍を通るで」
兵糧を運ぶ輜重部隊が、おっちゃんたちの前を通り過ぎる。
「今だ! 襲え!」
ドドンの合図と共に森からトロルが飛び出して、輜重部隊に襲い掛かる。
先頭を進んでいた兵士がすぐに異変に気が付き、向かってくる。
「総員撤退」の合図と共に笛が鳴らされる。
おっちゃんたちは我先にと森に逃げ込んだ。輜重部隊はおっちゃんたちを追ってこなかった。
ボロルが不満を漏らす。
「せっかく兵糧を奪えると思ったのに。もっと粘ってもよかったでしょう」
おっちゃんは、ボロルを宥(なだ)める。
「ええんやで。輜重部隊が襲われた事実が大事なんや。食糧を運ぶとモンスターが奪いに来る既成事実が必要なんや」
ボロルがわけがわからない顔をしていると、おっちゃんはドドンに呼ばれた。
「おっちゃん、特技の変身で人間に化けてくれ」
ドドンの言葉に、隊内のトロルがざわつく。
「ほんま、この特技は秘密にしておきたかったんやけどなあ」
おっちゃんはトロルの変身を解いて、人間の姿になる。
一部のトロルから感嘆の声が上がる。
「おい、あれを」とドドンが別のトロルに声を掛ける。
声を掛けられたトロルが、バックパックをおっちゃんに差し出した。
中には商人が良く着る、ゆったり目のクリーム色の服が入っていた。
おっちゃんは商人の服に着替えると、ドドンから金貨の詰まった袋を渡される
「これで人間の街に行って食糧を買ってくるのだ」
「へえ、わかりました」
おっちゃんは一番近くのウルリアンの街に行く。
ウルリアンは、人口三万人の大きな街で、人間の陣営に物資を運び出す拠点になっていた。
そこで、おっちゃんは穀物を扱う一番大きな商館に行く。
「お頼み申します。食糧を売ってください」
商館の番頭が出てくる。番頭は頭が禿げ上がった、感じのよい四十代の男性だった。
番頭は渋い顔で忠告する。
「食糧を売るのはいいけど、今は相場が高いから、他の街に持って行っても利益が出ないよ。儲けたいなら、他の街からウルリアンに運んだほうが利益が出る」
(親切な番頭はんやな。でも、うちらの狙いはちゃうねん。この街の食糧の高騰や)
おっちゃんは、本心を隠して告げる。
「他の街に持って行くのと違います。戦場に運んで、一儲けしようと考えています」
番頭が驚いた顔で警告する
「まさか、本陣へ食糧を運ぶのかい? 止めときな、軍隊の護衛がなきゃ不可能だよ」
おっちゃんは、うんうんと頷きながら滔々と語る。
「皆が、そう考える。だから、商機があると思いました。本陣へ食糧を売って大儲けや」
番頭は神妙な顔で引き止めた。
「止めたほうがいいって。リスクが大き過ぎる。モンスターに奪われて泣きを見るよ」
「ええから、売って。わいはこの商売に懸ける。金ならある」
おっちゃんは背負い袋から金貨の入った大きな袋を出す。
大量の金貨を見ると、番頭の顔色が変わった。
番頭は驚いた顔をして、意見を述べる。
「この額だとかなりの量になるよ。上手く行けば利益は莫大だけど、失敗したら大損だよ」
おっちゃんはぷいと横を向いて、冷たい態度を採る。
「一世一代の大博打や。売れないと拒否するなら、他に行くで」
番頭は儲け話をふいにしたくなかったのか、真剣な顔で承諾した
「わかった。三日、待ってくれ。商品を用意する」
(よし。これで、九割がた、食糧が手に入ったようなものや)
おっちゃんは食糧を運ぶための人足の手配もする。
人足がいる組合に行く。組合長は六十代で、白髪の小柄な男性だった。
おっちゃんは運ぶ量と場所を伝える。
組合長は曇った表情で、難色を示した。
「旦那、高い手間賃を貰える仕事は嬉しいです。だけど、うちらは戦えませんぜ。きちんと、冒険者を雇うなり護衛を付けてもらわないと、引き受けられません」
「護衛は高いから、つけん。それに、襲われたらどうせ守りきれん」
組合長は澄ました顔で仕事を拒絶した。
「それなら、引き受けられませんなあ」
「襲われたら、荷物を捨てて逃げてええ。そんで、手間賃は全額を前金で払う」
組合長が険しい顔で考える仕草をする。
「その条件なら、考えてもいいですが、皆に意見を聞きたいんで、一日だけ時間をください」
翌々日に、人足頭に会いに行くと、人足頭は厳しい顔で確認する。
「襲われたら荷物を捨てて逃げていい。また、全額前金なら引き受けます」
「そうか。なら、お願いするわ」
おっちゃんは人足頭に手間賃を払った。
翌日、人足たちが引く荷車に、大量の食糧を載せて、街道を進む。
本陣とウルリアンの街の中間地点で、ドドンが襲ってきた。
おっちゃんは大声で叫ぶ。
「あかん、モンスターや! 撤退や!」
おっちゃんは真っ先に逃げた。人足たちも我先にと食糧を放棄して逃げ出した。
少し経ってから、おっちゃんは現場に戻る。
ドドンがドラゴンの背に急いで、食糧を積み替えているところだった。
「これで良かったでっか」
ドドンが満足した顔で告げる。
「上出来だ、おっちゃん。これで、食糧の値段は上がる。そうすれば、おいそれと食糧を買えなくなるぞ」
【第十四昼 おっちゃんと兵糧攻め】
おっちゃんたちの部隊が帰ってくると、数日遅れて他の部隊とドラゴンが帰ってくる。
どのドラゴンも、食糧をどっさり持って帰ってきた。
おっちゃんとボロルは城の上部にあるドラゴンの着陸ブースで、人間の街から手に入れてきた食糧を城の中に運び込む仕事をしていた。
ボロルが、次々と到着するドラゴンを見て驚く
「こいつは凄い量ですね。いったい、いくらあるんやら」
「ウルリアンへと続く街から運んできた食糧やね。きっと今頃、ウルリアンで食糧が高騰して、本陣へ送るどころの騒ぎやないで」
ボロルが機嫌よく意見を述べる。
「これで人間たちも、兵を引くしかなくなりますね」
おっちゃんはまだ油断していなかった。
「さあ、どうやろうな。戦争って、どこでどうなるか、わからんからな」
翌朝、悪い知らせが届いた。城の上にいた見張りのオーガたちが沈んだ顔で噂する
「人間の大草原の王の騎兵隊が、兵糧を持って馳せ参じるために、国を出たそうだ」
「敵が増えたうえに、兵糧が補充されるのか。これは、雲行きが怪しいな」
噂を聞いたボロルも、渋い顔でおっちゃんに愚痴る。
「せっかく人間たちの兵糧を奪ったのに、外から兵糧が持ち込まれるなら、今までの作戦が、意味がなくなりましたね」
「そんなことは絶対ないで。大草原の王が持って来た兵糧かて高が知れとる。それがなくなれば、今度こそ人間側はしまいや」
ボロルが不安な顔で意見する。
「なら、人間は兵糧がなくなるまえに大規模攻勢を懸けてきますよ」
「そうなる前に、ウィンケル卿は動くな」
おっちゃんたちに再度の出撃命令が下った。任務は少人数による熟練魔術師の護衛だった。
五人の熟練魔術師を護衛して、おっちゃんたち三十名のトロルが出発する。
出発した先は、城の上流にある湖だった。
湖の近辺では、戦争で村を放棄してきた異種族たちが集まり、既に土木工事を開始していた。
熟練魔術師に、オーガの技師が真剣な顔で告げる。
「工事は完了しています。あとは、湖に水を貯めるだけです」
熟練魔術師も、真剣な顔で応じる。
「わかった、ご苦労。あとは、こちらでやろう」
ボロルがそっと、おっちゃんに尋ねる。
「これから何が起きるんですか?」
「何って、湖の水を満水にして、決壊させるんや」
ボロルが意図(いと)を察して、理知的な顔で語る。
「大草原の王が持ってきた兵糧を水で押し流して、使えなくするんですね」
「そうやで。大草原の王が到着する頃に水が満水になるように、計算してある」
熟練魔術師が魔法を唱えると、空がにわかに曇って雨が降り出した。
おっちゃんとボロルは雨避けの小屋に避難する。
ボロルが冴えない表情で、否定的に意見を述べる。
「でも、ウィンケル卿も思い切った作戦を採りますね。人間の本陣が水浸しになるのなら、もう少し低い場所にある『狂王の城』だって、打撃を受けますよ」
「そうは、ならんねん。『狂王の城』の地下には、わいらの職場の 大空洞があるやろう。水攻めが起きると、水は水路を通って、全て大空洞に流れ込むねん」
ボロルが「そうだったのか!」といわんばかりの顔で驚く。
「もしかしたら、『狂王の城』の大空洞って、水攻め対策のための空間だったんですか?」
「知らんかったんか? 平時の時はダンジョンで、有事の時は水の逃げ場になっとったんやで」
ボロルが神妙な顔で頷く。
「今回は俺たちが水攻めに湖を使いました。だけど、人間たちも考える策だから、対策があって当然か」
「そうやで、『狂王の城』は色々と考えて建てられておるんや」
三日後、熟練魔術師の警護をしている時のことだった。
幕舎に真剣な顔のコボルドの伝令が駆け込んでくる。
「大草原の王が兵糧を持って本陣に援軍として到着しました」
熟練魔術師がオーガ技師に険しい顔で声を掛ける。
「水の準備はできている。今晩、水攻めを決行するぞ」
その日の晩に、湖は決壊して、大量の水が人間の本陣を襲った。
作戦終了後、おっちゃんたちの部隊は速やかに『狂王の城』に入った。
おっちゃんが休憩していると、ボロルがご機嫌な顔でやって来た。
「湖の水は濁流となり、兵糧を押し流したそうです。押し流された兵糧は『狂王の城』に到達して、地下空洞に流れ込んでいました」
「そうか。これで、人間側は兵糧を失った。調達もできん。兵を引くしかないな」
三日後、人間側が撤退の準備を始めると、ウィンケル卿が動いた。
ウィンケル卿は部隊を出して、撤収中の人間の本陣に攻撃を仕掛ける。
人間たちはまともな交戦ができないまま、散り散りなって逃げ帰るしかなかった。
人間がいなくなると、人間側が置いていった物の回収と大掃除で、おっちゃんとボロルは大忙しだった。
片づけが終わる頃にニュースが入ってくる。
「人間たちが、人間同士で戦争を始めた」
(敗戦で弱くなったところを、仲間割れして襲撃しあうとは、ほんま人間とは恐ろしい生き物やなあ)
かくして『狂王の城』を攻略しようとして兵を出した人間の連合軍は敗北した。
この敗戦が切っ掛けとなり、人間側の連携は崩れる。『狂王の城』を軍隊で落とそうと考える人間は現れなくなった。
【第十五昼 おっちゃんと戦後処理(前編)】
人間の軍隊が撤収した後、大洞窟では水抜きが行われ、元のダンジョンに戻っていた。だが、戦争の影響で冒険者はめっきり減っていた。
暇そうにしていたボロルが話し掛けてくる。
「冒険者がまったく来なくなりましたよね」
「人間は敗戦のあと、内部分裂して、抗争を繰り広げとる。冒険者のような、戦える若い人間は徴兵対象や」
ボロルが苦い顔で辛辣(しんらつ)に評する。
「なんかなあ、こんな事態になるなら、戦争なんて仕掛けて来なければ良かったのに」
「起きた戦争を、こうなっていたらとか、ああなっていれば、と考えてもしゃあない」
ボロルが冴えない顔で意見する。
「おっちゃんが指摘する通りなんですけどねえ」
「今日はこのあと会議やから、早めに上がるわ」
「あの、冒険者を呼び戻すための企画会議ですか? 行ってらっしゃい」
『狂王の城』に会議室に行く。
会議室には様々な担当部署から二十名の種族が参加していた。
議長のドドンが開会を宣言して、意見を募る。だが、名案は一向に出ない。
(無理もないか。兵糧の買い占めに多額の金を使ったから金はない。その兵糧も恩賞として作戦に協力してくれた村に配ったから、なくなってしもうた)
会議に参加していたオーガが、渋々の顔で意見を出す。
「いっそのこと、罠を止めて、攻略難易度を下げてはどうでしょう?」
ドドンが苦渋の顔で反対する。
「難易度を下げる策は採れない。ウィンケル卿から直々に、難易度は下げるなと指示された」
会議の空気が重くなる。龍人族の男がむすっとした顔で発言する。
龍人族とは龍の顔を持ち、体は鱗が生えた人間に似た種族だった。
「ならばいっそ、こちらから人間の村を襲ってはどうでしょう?」
ドドンが苦い顔で問う。
「それで、どうなる?」
龍人族の男が厳しい顔で伝える。
「きっと、人間たちはまた我々を脅威に考え、戦争を止めて結束するでしょう。そうなれば、また冒険者はやって来る」
「わいは人間の村を攻めるのは反対ですな。村人は冒険者やない。覚悟も武器も持たん存在ですわ。そんな弱い者虐めみたいな策は採用すべきではない」
コボルドが険しい顔で反対する
「戦争は人間が始めたんだ。なら、人間にも相応の犠牲を払ってもらおう」
「そうだ」「そうだよね」と会議は、人間たちに脅威を知らしめて冒険者を集める方向で話が進んでいく。
反対する人物はおっちゃんの剣の師匠である龍人族のドラニアと、あと一人だけだった。
十七対三で、人間の村を襲う作戦は了承された。人間の村を襲う役目に、おっちゃんは選ばれた。
拒否してもよかった。おっちゃんは自分がいればまだ虐殺を止められると思い、拒否しなかった。
おっちゃんたち三十人からなるモンスター部隊が、近隣の人間の村に向かった。
(覚悟も武器も持たん人間の村を襲うのは、気が引けるで)
最初の村に着いた時に、おっちゃんが見た光景は、焼き払われた村だった。
「何や、この村? もう襲撃があった後やで。他の部隊が来た後か?」
部隊長のドラニアが、困惑した顔で告げる。
「この村の担当は我々だ。区割りは厳密だから、先を越された事態はない」
「そうですか。なら、次の村に行きますか」
次の村に行ったが、誰もいなかった。
家々を調べると荒らされた痕があり、金目の物も食い物もなかった。その、次の村に行っても、同じ状況だった。ただ、その村にただ一人だけ老婆が残っていた。
ドラニアが困惑した顔で老婆に尋ねる。
「村の人間はどうした?」
老婆は呆然とした顔で答える。
「男たちは兵隊に持っていかれて、女は連れて行かれた。金品と食い物は全て奪われた」
「誰にやられたんだ」
「人間だよ」と老婆は悲しい顔をして泣き出した。
おっちゃんたちはやるせない気持ちでダンジョンに帰還した。他の部隊が戻ってきたので情報交換をする。近隣の村の惨状は変わらなかった。
(これは思ったより、大変な事態になっとるのう。ダンジョンに来るどころではないわ)
緊急の対策会議が開かれる。他のモンスターたちに人間の村の惨状が報告されると、会議は重苦しい雰囲気に包まれた。
ドドンが険しい顔で苦しげに述べる。
「参ったぞ、これは。ここまで戦争の災禍(さいか)が拡がっているとは、思いもよらなかった」
ドラニアが苦渋に満ちた顔で発言する。
「かといって、何もできませんでした。では、ウィンケル卿に合わせる顔がないぞ。冒険者不足は緊急の課題だ」
おっちゃんは迷った。
(これを発言したら、ここにいられんくなるかもしれん。せやけど、人間の自滅を黙って見ていれば、結局はダンジョンが廃れる)
おっちゃんは重苦しい雰囲気の中で発言した。
「こうなったら、この『狂王の城』の近くにウィンケル卿の荘園を作って、人間を入れましょう」
おっちゃんの言葉に、皆の顔が歪む。
コボルドが怒って発言した。
「人間の村をウィンケル卿の所領に作るだと? 貴様は正気か?」
「そう反論されたかて、これをほっといたら、事態が悪化するだけでっせ。それに、人間の住処が近くにあるダンジョンかて、ありますやろう」
ドラニアが戸惑った顔で発言する。
「ダンジョン持ちの都市のことか? ダンジョンに併設された人間の都市は、あるにはある。だが、人間の村をここの近くに作れば、次の戦争の時、人間に利用されるぞ」
「戦争の際に村が人間側に付くリスクはあります。でも、このままだと、共倒れや」
オーガが憤然とした顔で反対する。
「でも、ウィンケル卿の荘園は問題があるだろう。ウィンケル卿が、自分を倒す人間の拠点をウィンケル卿自身で作ったとなれば、笑いものだ」
「なら、他にええ案がありますか?」
おっちゃんの言葉に皆が黙る。
議長のドドンが、重い口を開く。
「ウィンケル卿に解決策がありませんでした、とは回答ができない。荘園の案は一応は上げてみる」
ウィンケル卿がおっちゃんの案を採用する予感があった。
この予感が当れば、代官としておっちゃんが派遣されると推測していた。代官の就任は断りたかったが、他にやる人材はいない。
(代官になったら、最終的にはここを去らなきゃならん。せやけど、しゃあない。ウィンケル卿には拾うてもらった恩がある。たとえ『狂王の城』から消える展開になっても、恩返しは、せなならん)
【第十六昼 おっちゃんと戦後処理(中編)】
おっちゃんの献策は、ウィンケル卿に理解された。
一週間で『狂王の城』のすぐそばに人間の村が作られると発表された。
発表の翌日に、おっちゃんはドドンに呼ばれた。
ドドンが困った顔で、やんわりと申し出た。
「おっちゃん。お願いある。新たにできる村の代官をやってくれ」
(やはり、こうなったか)
「わかりました。ほな、代官をやらせてもらいます」
ドドンはすまないとばかりに頭を下げた。
「本当に申し訳ない。行く行くは、おっちゃんにはフロア・ボスを任せたかったんだが、こんな事態になってしまった」
「ええですわ。わいはしょせん、中途採用です。ダンジョンの幹部候補になる者に人間の村の代官をやらせれば、キャリアに傷がつきます」
「そうか、わかってくれるか」
おっちゃんは、その日、ダンジョンを去る準備をしてボロルに挨拶をする。
「ボロルはん、今日まで、ありがとうな」
ボロルは納得が全然いかない顔をしていた。
「なんで、おっちゃんがダンジョンを去らなきゃならないんですか?」
「止むを得ないねん。上の決定や」
ボロルは寂しげな表情をする。
「もう、戻って来ないんですか?」
「決定事項やない。せやけど、慣例として、いったん外に出た者はダンジョンには戻れん。だから、もう、ここに戻ってくる未来はない」
ボロルは沈んだ表情で悲しさを表現する。
「そんな、寂しいですよ」
「でもな、こういう別れもあるねん。ほな、達者でな」
おっちゃんは次の日から村の代官として、村造りに携わる。
村造りに関与したモンスターには不満がありありとあった。だが、ウィンケル卿の命令とあれば、従わないわけにはいかない。
一ヶ月足らずで、八十世帯が住める村ができた。村ができると、おっちゃんは村ができたことを通知するビラを、ドラゴンから撒いた。
一週間もすると、難民になった、三十人からなる人間の一団がやってきた。
最初は警備モンスターが常駐するので、人間は近寄ってこなかった。
おっちゃんは人間の姿で近づいて、声を掛ける。
「ここは、ウィンケル卿が治めるモンスターが支配する村や。税を納める限り攻撃はされんで」
難民のリーダーと思われる三十代の精悍な顔つきの男性が前に出る。
男性の服装は汚れてボロボロ。黒髪もボサボサだったが、凛々(りり)しい眉をしていた。男性が尋ねる。
「それで、税はどれぐらいなんですか?」
「収穫物の三割や」
「本当に、それだけですか?」とリーダーはおっちゃんの言葉を疑った。
「そうやで。まあ、ここで話しているのもなんやから、うちに来いや」
おっちゃんは難民を村に招いて、パンとスープで温かく迎えた。
時が経つと、村を追われたり、村を捨てたりした人間が、次々にやって来た。
最初のうちはおっちゃんの言葉を疑った難民だが、他の人間が村にいると安心した。
時折、兵士と思われる小集団が来る度に村の鐘を鳴らす。鐘が鳴ると、城の上にオーガの弓兵が現れて威嚇(いかく)する。
分が悪いのは明らかなので、兵士の集団は逃げ出す。
おっちゃんは兵士の集団に、大声で警告する。
「ここはウィンケル卿の荘園じゃ。手を出したら、ただでは済まんぞ」
ウィンケル卿の庇護がある荘園を、下手に刺激すると危険と人間は考えた。人間は手を出してこなくなった。
三ヶ月が経ったある昼下がりの頃、二人の冒険者がおっちゃんの家を訪れた。
冒険者の一人は男性で大きな剣を持った、がっしりした体格の髭面の戦士だった。もう一人の冒険者は、赤いローブを着た女性の若い魔術師だった。
おっちゃんは茶を出して、二人を持て成した。
「こんな辺鄙(へんぴ)な村によく来てくださいましたな」
戦士が真剣な顔で応える。
「まさか、本当にモンスターに支配された村があるとは思わなかった」
「悪政はモンスターより怖い、言う話ですわ。ここでは、村人は税を納めれば、ダンジョン以外では危害を加えられません」
戦士が顰(しかめ)っ面で聞く
「では、ダンジョンに入ったら?」
「ダンジョンでは話は別や。そこは、他のダンジョンと一緒。殺し殺されの世界ですわ」
戦士が気を楽にして訊く。
「では、我々がダンジョンに入ろうとしたら、止めますか?」
「どうぞ、ご自由に。冒険者がダンジョンに入るのは止めません。あと村の中央にある酒場ですけどな。あれ、近々、冒険者の酒場にしよう思っておりますのんや」
戦士が馬鹿にしたように意見する。
「それじゃあ、ダンジョンを攻略してくれと認めているようなものですな」
「冒険者がダンジョンに行くのは自由です。もっとも、死んでも知りませんけどな」
戦士は困った顔で告白した。
「実は私たちは、村の代官を暗殺するように依頼を受けてきました」
おっちゃんは別に驚かなかった。
「やはり、そう来ますか」
戦士は辛そうな表情で告げる。
「でも、この村の状況を見て決心が鈍りました。私たちのしようとしている仕事は正しいのか」
「冒険者の仕事で、暗殺は範囲外とする人たちは多いからね」
窓の外を見ていた若い女性魔術師が意見する。
「仕事はキャンセルね。ここで代官を斬ったら、生きてここから出られないわ」
戦士が厳しい表情で尋ねる。
「モンスターに囲まれているのか?」
女魔術師は素っ気ない顔で軽い調子で尋ねる。
「いいえ、村人に囲まれているわ。ここをもし出るなら、罪のない村人を大勢斬らないと、帰れないわ。貴方にそれができる?」
「できないな」と戦士は諦めた口調で告げる。
戦士は神妙な顔で訊いてきた。
「代官。我々にできる仕事は、何かないか?」
「そうやね。なら、村に冒険者の酒場があるって、宣伝してもらえますか」
戦士が意外そうな顔で確認する。
「そんなことで、いいのか?」
「百姓は畑を耕せばええ。冒険者はダンジョンに行ったらええ。やりたくない戦争なら、しなくてよろしい。ただし、ダンジョンの中では気遣い無用やで」
二人の冒険者はその後、村の酒場に寄ってから帰っていった。
【第十七昼 おっちゃんと戦後処理(後編)】
村は避難してくる難民のために拡張された。ウィンケル卿も村を拡張する資材をダンジョンから提供してくれた。
酒場には戦争に嫌気がさし、ダンジョン探索を懐かしむ冒険者が集まってきていた。
おっちゃんには冒険者には「ダンジョンの中は別やで」と強く釘を刺すだけで、行動に制限は懸けなかった。
初心者はおっちゃんの言葉を甘く見て、手痛い目に遭った。だが、慣れた冒険者は割り切って、村とダンジョンでは心を切り替えて挑んでいた。
そんなある日、おっちゃんの許にドドンが尋ねてきた。ドドンはとても申し訳なさそうな顔をしていた。
「おっちゃん、その、すまない。代官を降りてくれ」
おっちゃんはドドンの言葉に驚かなかった。
いつかはこういう日が来ると、覚悟していた。
「村の警備はどうします?」
ドドンが曇った表情で、計画を語る。
「警備に異種族は使わない。これからはロック・ゴーレムにやってもらう。つまり、この村の警備から、トロルやオーガなどの種族は手を引く」
「なら、わいの処遇はどうなりますか?」
ドドンは視線を合わさず、たどたどしく発言する。
ダンジョン内では決して見せない弱りようだった。
「それ、なんだが、村の人間と親しくなったおっちゃんは、ダンジョン勤務に戻るのは無理だろう」
おっちゃんは正直に答えた。
「仲良くなった冒険者も結構いますからな。ダンジョンで遭ったらお互いにやりづらいのは確かですわ」
ドドンの視線が泳ぐ。ドドンは気が咎めるのか苦しそうな顔で頼んだ。
「そこでだ、ウィンケル卿が推薦状を書いてくれる。だから、推薦状を持って、他のダンジョンに行ってくれないか」
(やはり、そうなるか、予想した通りやな)
予想はしていた。だが、いざ伝えられるとショックだった。
おっちゃんが黙ると、ドドンが頭を下げ懇願する。
「おっちゃんを切り捨てるような真似をして、非常に心苦しく思う。だが、これが、ダンジョンにとって一番いいんだ」
(ダンジョンの運営を一番に考えるのはダンジョン・モンスターの務めやからなあ)
おっちゃんは優しい口調で伝える。
「頭を上げてください。わかりました。後任の代官を人間から指定したら、この村を去ります」
三日後、おっちゃんは村人の中から後任の代官を選んで、代官宅に呼んだ。
後任の代官に選んだ人間は、最初に村にやってきた難民のリーダーの男だった。
「悪いが、わいの代わりに、代官をやってくれんか」
男は躊躇(ためら)いがちに訊いた。
「俺なんかで、いいんですか?」
「すまんな。わいは他の村に赴任する話がある。だから、もう、ここにはおれんのや」
男は決意の籠もった顔で了承した。
「わかりました。そういう事情なら、引き受けます」
おっちゃんは後日、引継ぎを済ませ、『狂王の城』所属の高位魔術師に、戦禍の及ばない場所に送ってもらった。
高位魔術師が帰ると、おっちゃんは平原に伸びる道の真ん中に一人でいた。
「これで、就職活動からのやり直しやなあ」
おっちゃんはどこまでもまっすぐ伸びる道を一人で歩き始めた。
【『狂王の城』編・了】
【特別編 「マリアと聖騎士の謀反」】
※このショートストーリーは、三巻の内容および、その巻末ショートストーリーと合わせてお楽しみください。
人々が眠りに就く安らかな夜。マリアの耳に『認めよ』と、威厳のある男の声が聞こえた。
夢とは思えない圧倒的な現実感を持った声により、マリアは目が覚めた。
簡単には再び眠りに就けそうになかったので、水を飲みに水飲み場に行く。
水飲み場には、八人の僧侶がいた。
「あれはいったい何の声だ?」と若い僧侶たちは真剣な顔で話し合っていた
老いた僧侶も水を飲みにやってくる。老いた僧侶が神妙な顔で教える
「前に二度、聞いた経験がある。あれは神の声じゃよ」
若い僧侶が困惑した顔で老いた僧侶に尋ねる。
「いったい、神は何を認めろ、と仰(おっしゃ)ったのでしょう?」
老いた僧侶は、厳粛な顔で告げる。
「それはわからん。だが、教皇庁は神託により、重要な決断をしたのだろう」
若い僧侶は神託の内容をあれこれと話し合う。だが、マリアは議論に加わらず部屋に戻った。
(何か、今日、マキシマムは大きな決断をした気がする)
翌朝になると、審問会で何が審議されていたかの情報が漏れる。
「モンスターに人と同等の権利を認める」
想定外の内容に教皇庁は騒然となっていた。長年モンスターと戦っていた聖騎士からの反発が強かった。
マリアはいつぞやのお礼に、ホフマンに苺ジャム・サンドをプレゼントしようとしていた。
ホフマンの居場所を尋ねると、仲間の聖騎士が「庭に行った」と教えてくれた。
庭にいるホフマンを見つけた。挨拶をして、いつぞやの御礼をしようと思った。
だが、ホフマンに先に声を掛ける聖騎士がいた。声を掛けた聖騎士にはただならぬ気配があった。気になったので木陰からそっと二人の話を盗み聞きする。
聖騎士の一人は激しく憤っていた。
「馬鹿げている。モンスターを異種族と呼び、人と同じ権利を与えるなんて絶対に間違っている」
(やはり、審問会の決定が、問題を引き起こしているようね)
ホフマンが穏やかな顔で宥める
「でも、ヨーゼフ。これは、猊下のご判断ではない。神の意志によるものだ。聖騎士たる我々は神の意志に叛(そむ)いていいわけがない」
ヨーゼフが怖い顔で問い質す。
「なあ、ホフマン、本当に教皇庁に神なんているのだろうか?」
ヨーゼフの言葉にマリアはぎょっとした。
神の存在を疑うなど、教皇庁では口にしてはいけない言葉だ。
ホフマンは困惑した顔で意見する。
「おいおい、何を言い出すんだ、ヨーゼフ。神はいて、常に世界を見ておられる」
ヨーゼフが厳しい顔で反論する。
「俺は知っている。教皇庁に神なんていない。教皇庁の地下にあるのは大きな喋る魔道具だ」
ホフマンはすぐに他人目(ひとめ)を気にして宥めようとする。
「馬鹿な話をするんじゃない。下手をすれば左遷されるぞ」
ヨーゼフはいきり立った。
「これは大事な話だ。俺は神を信じるがゆえに、教皇庁が神と呼ぶものを疑う。本当に神がいるのなら、モンスターを人間と同様に扱えとは命じない」
ホフマンが青い顔をして、考え直すように促す。
「おまえ、まさか、謀反を考えているのか? 馬鹿な真似はよすんだ」
ヨーゼフが暗い顔で断言する。
「違う。これは真の改革だ。神の信徒はマキシマムではない。前線で戦う俺たち聖騎士だ」
ホフマンはどうにかヨーゼフを止めようとしていた。
「まさか。お前、神に刃を向けるのか? 死ぬぞ!」
ヨーゼフは厳しい顔をして強い口調で教える。
「俺には偽りの神に立ち向かう仲間がいる。殉教も辞さない」
ホフマンは弱った顔で、思い止まらせようとする。
「無理だ。神は『使徒ケプラン』と天使たちに守られていると聞く」
ヨーゼフは暗い顔で淡々と告げる。
「それは、権威付けのための出任せだ。神の間へと続く前室にあるのは、単なるでかい水晶像だ。天使なんてのも、いやしない。全ては教皇庁の欺瞞なんだ」
ホフマンは怖い顔で質問する。
「だが、大扉の前には四人の聖騎士がいるぞ。ヨーゼフは仲間と戦うのは、平気なのか?」
ヨーゼフは眉間に皺を寄せて策を語る。
「平気じゃないさ。でも、そこは、ちょいと頭を伝えば問題ない。薬入りの飲み物を渡せば眠らせられる」
ホフマンは大いに困っていた。
「そうかもしれないが、本当に神に刃を向けるのか?」
ヨーゼフは真剣な顔で頼んだ。
「目を覚ましてくれ、ホフマン。教皇庁の地下に神なんていない。魔道具を破壊して皆に教皇庁には神がいないと教えてやらないと、モンスターが街に入ってくるぞ。我々はモンスターと戦う正義の騎士だ」
「わかった。一晩、考えさせてくれ」
聖騎士の謀反の情報を聞きマリアは怖くなった。ただ、黙ってヨーゼフとホフマンが立ち去るのを待った。
二人がいなくなってからも、すぐに木陰からは出ていなかった。
「駄目よ。そんな、信徒同士で争うなんて」
だか、ヨーゼフの決意は堅そうだった。
「マキシマムに、猊下に、知らせないと」
聖騎士の一部が謀反を起そうとしている情報を知らせるために、マリアはマキシマムの許に走った。